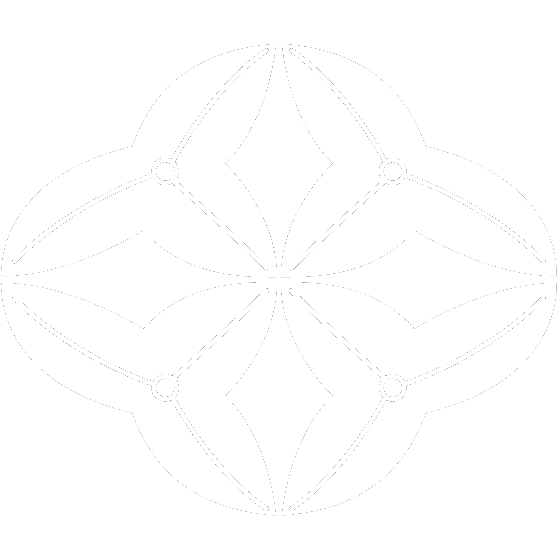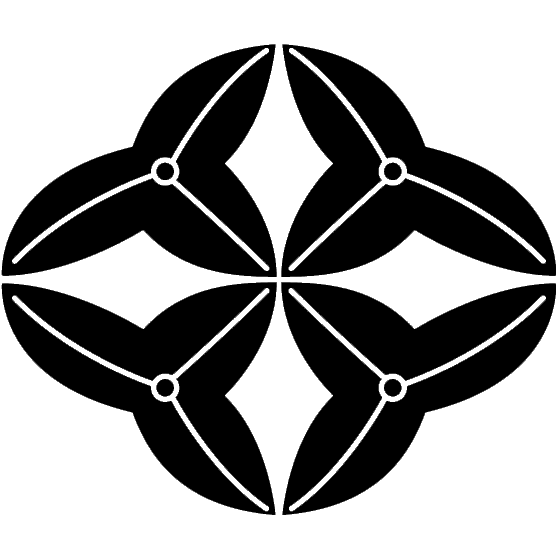
温泉寺茶話
こころのご供養
昨年来のコロナ禍、心よりお見舞い申し上げます。
全国的に、故郷へなかなか帰省することが叶わない方も、大勢おみえになると思います。帰省しようとする方も、帰省を待っておられる方も、感染症を理由にそれが叶わない状態が続いております。とても残念なことです。
そういう私も、実は随分長い間、帰省できておりません。両親にも、いつから会っていないのかわかりません。宗教者でありながら、実は祖父母やご先祖様のお墓参りも怠っています。
この春は、祖母の17回忌でした。ですが、実家のほうで早々に、お互いの健康維持のためにと、帰省することはやめておこうということになりました。実家近くの親戚だけを呼んで、無事に法要を済ませたようです。
両親が共働きの家庭で育った私は、小さいころはいつも祖母と一緒にいました。と言うより、いつでも祖母が一緒にいてくれていたのです。だから、17回忌に際して、ただ郵便局からお供えを送るだけのご供養は、何だか淋しく、情けない心地でした。
そんな私の想いを救ってくれた俳句があります。
その人の 足跡ふめば 風薫る
松尾芭蕉没後200年の明治26年、芭蕉を偲んで正岡子規が残した俳句です。その年は、芭蕉の200年法要はもとより、芭蕉追悼記念イベントが各地で盛大に行われたそうです。しかし、間接的にも芭蕉との縁を持ち得てなかった正岡子規は、ただ1人、静かに先の俳句を詠んだのでした。
『その人の足跡をふむ』ということは、『その人を偲ぶ』ことというふうに理解しています。時を問わず、場所を問わず、ただ「その人」を想い偲んでおれば、きっと『その人の風』が自分にも薫ってくるのだと、とても励まされております。
私たちはいつでもどこに居ても、大切な人のことを想うこと(偲ぶこと)ができます。それは直接的なご供養でなくとも、立派な心のご供養であります。この『心のご供養』こそが、今私たちにできる、祖先への最大のご供養ではなかろうかと存じます。
皆様方のご健勝をお祈り申し上げます。
2021.05.28
コロナ有り、紅葉も有り
秋がやってまいりました。新型コロナウイルスが流行している中でも、日本の四季はちゃんと動いていることを実感します。
春にはきちんと桜が咲きました。夏の猛暑の朝、朝顔がたくさん花を咲かせていました。そして今、たまに訪れる涼しい秋風が本当に心地よく感じられます。
この涼しい秋風に癒された俳人が江戸時代にもありました。元禄2年、奥の細道の大紀行を巡った松尾芭蕉です。まだまだ残暑厳しい8月(新暦では今頃)、芭蕉は加賀国・那谷寺に立ち寄ります。私自身も那谷寺へお参りさせていただいたことがありますが、境内を奥へ進むと、実に雄大な白い岩壁を望むことができます。その壮大さ、美しさに目を奪われてしまうのですが、芭蕉も同じような気持ちで望んだことと思います。そして厳しい残暑を一瞬でも忘れさせてくれる一陣の風に、芭蕉は心奪われたのではないかと思うのです。
石山の 石より白し 秋の風
今、ここで、本当に生かされているんだ!という喜びが伝わってまいります。
コロナ禍により、いろいろな面で不都合が生じている昨今ですが、そんな中でも秋風は必ず吹いてくれるものと信じています。
そして、秋の深まりの中で、今年もモミジの紅葉を待ちたいと思います。(見頃は11月中旬です)
2020.09.14
万葉集に込められた願い
『令和』に改元されて2年目。希望に満ちた新時代!
と思っておりましたが、令和2年はたいへんな年になってしまいました。新型コロナウイルスの猛威。未だワクチンや特効薬の開発には至らず、その脅威は増すばかりです。
その上、九州地方を襲った集中豪雨。被災され多くの尊い命も失われました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。また被災されて今なおご苦労されている大勢の方を思うと、言葉もありません。どうか、一日も早く穏やかな日が訪れますようお祈りするばかりです。
周知の通りですが、新元号『令和』は万葉集に由来します。その万葉集の編者にはいろいろな説があるようですが、最も有力な編者に挙げられるのが、奈良時代の公卿・大伴家持です。万葉集に納められた和歌、全4516首のうち、実に1割以上の473首が大伴家持の和歌であり、万葉集最後の和歌・4516首目の和歌も、大伴家持の作であります。
新しき 年の始めの 初春の 今日降る雪や いや重け吉事
【あらたしき としのはじめの はつはるの きょうふるゆきや いやしけよごと】
大伴家持は貴族社会の中でも有力者であったことは間違いありませんが、当時の最高権力者であった橘氏と、新興勢力の藤原氏との狭間に立たされ、苦しい立場におかれていたことも事実であります。両者の権力抗争に巻き込まれたために、奈良の都に居るのではなく、度々地方へ赴任しているのです。越中国守(越中国の知事)として現在の富山県高岡市に赴任していたことは有名です。この頃に家持は多くの和歌を詠み残しました。
そして、天平宝字2年(758年)、家持は因幡国(現・鳥取県)へ赴任します。これは事実上の左遷であったそうです。ここで迎えた最初のお正月に、先ほどの和歌を詠み、これ以降家持は和歌を残しておりません。そしてこの和歌が、万葉集最後の和歌になりました。
新しき 年の始めの 初春の 今日降る雪や いや重け吉事
当時、元日に降る雪はその年の豊年をもたらすと言われ、非常に縁起の良いものとされていたそうです。左遷という屈辱的な事実を受け入れなければならなかった家持は、元旦の雪が降り積もるように、吉事(良い事)もたくさん重なりますように・・・と願ったものだと思います。それは家持自身にとっての吉事を願うのみならず、「どうすることもできない現実」を受け入れざるを得ない世の中全体に向けられた願いでもあると思います。その願い「世の中の平安」こそが、万葉集に込められた願いではないかと思うのです。
私たちはまさに今、「どうすることもできない現実」を数多く突き付けられています。奇しくも万葉集に因んだ『令和』という時代に。
大伴家持の願い・万葉集の願いである「世の中の平安」を、今はただただ願い、祈る時だと思います。
新型コロナウイルスの災禍、多くの天災によりご苦労を強いられている方々に、一日でも早く心穏やかに過ごせる日が来ますように、お祈り申し上げます。
2020.07.10