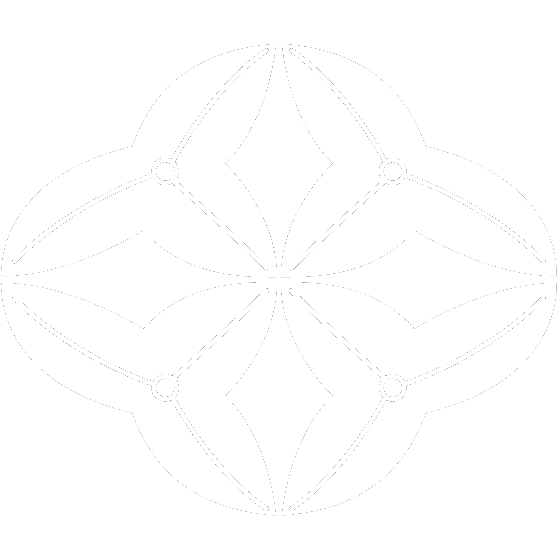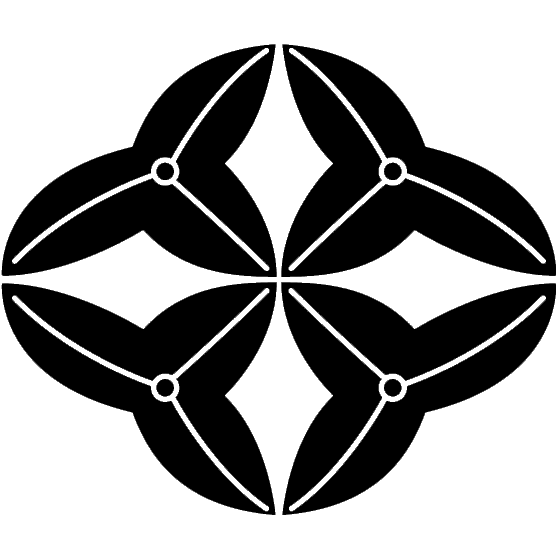
温泉寺茶話
今、できること
このたびの東日本大震災にては多くの尊い命が失われてしまいました。それと同時に大切なもの全てを失った方々が、被災地の多くの避難所にて寒さに耐えながら物不足な中での生活を強いられています。
今、私にできることは限られてはいますが、被災なさった方々の身に自分の身を置き換えて実行していきたいと思っています。
ところで私たちの所属である臨済宗には、このような言葉が伝わっています。
「照用同時」~しょうゆうどうじ~
中国の碧巌録という語録に出てきます。「照」は見るという意味。「用」は動くとか、働くという意味で、要するに見ることと動くことが同時に行われることです。例えば、歩き始めた赤ちゃんがヨチヨチ歩きしていて転びそうになったとき、とっさに手を添えてあげる働き・動きを思い浮かべてみられたらわかりやすいでしょう。
この時のポイントは、転びそうになった赤ちゃんに、手を差し伸べて介添えしたことに対して恩をきせたり、後から何かを求めたりは決してしないことです。誰でもそうですよね。赤ちゃんは可愛らしい微笑みを見せてくれ、こちらもそれを見て心が和みます。ただそれだけなんです。これを「照用同時」といい、本当の助け合いというのではなかろうかと思います。
臨済宗の根源的存在である達磨大師(ダルマさま)はここのところを強く伝えておられます。
当時の中国、梁の皇帝武帝に歓迎歓待されたときにさえ、自他不二、一切空の立場を貫かれました。梁の武帝という皇帝は深く仏教を信仰されており、多くの寺院建立、僧侶への布施を惜しみなく続けておられました。仏心天子とよばれるほど、仏教を大切にして下さっていたのです。その武帝に、自分はどれほどの功徳があるのかを尋ねられ、
「無功徳!!」
と、いともあっさり申されてしまいました。
達磨大師の意図は、もう皆様おわかりでしょう。 つまり、仏教に対して尽力なさった武帝の行動は素晴らしいのですが、そこに自分だけの功徳を求めてはいけなかったのです。達磨大師は、功徳の有る無しという世界すら、消し飛ばされたのです。
ちなみにこの時、武帝は激怒し、達磨大師を追い返されたのですが、後にこの達磨大師の教えを深く理解され、もう二度と対面されることは無くても、仏教を信仰し続けられたのでした。
震災後、日本全国の人が皆、被災者の方々に向けて、今、自分にできることは何かを考えながら、そして実行されながら生活しています。一人一人の努力は決して大きいものではなくとも、その努力は輝きを放つ貴重なものです。恐らく皆が自ら求めるものの無い「照用同時」の世界を実行しているときではないかと思います。
求めるものがあるとすればただ一つ。被災者の方々の安全確保・早期復興、それだけです。私自身も微力ながら、今できることをさせていただきたいと思います。
最後に、文章中に適切ではない例え、表現がありましたらお詫び申し上げます。未熟者の寝言だと理解していただけましたら幸甚に存じます。
2011.03.26
新年の梅三輪
皆さま、あけましておめでとうございます。
相変わらずノラリクラリの茶話にお付き合いいただき、御礼申し上げます。
今年も1年、宜しくお願い致します。
さて、温泉寺の年越しですが、毎年「除夜の鐘・元旦修正会」という法要を営んでおります。参拝者には自由に除夜の鐘をついていただき、本堂で自由にお参りされたのち、お1人お1人にお屠蘇を振る舞い、新年のご挨拶をして記念品(干支色紙など)をお渡ししています。おかげ様で近年、この初詣の参拝者の数が急増しています。今年は除夜の鐘が300発以上、下呂の街に鳴り響きました。
そうした中、住職は本堂はじめ諸堂にて1年間の国家平安、五穀豊穣、参拝者の健康安全を祈願しています。境内には当然スタッフの方たちが火を焚いたり、参拝者の誘導、足元注意を呼び掛けて下さっています。寒い中本当にありがたいです。
ところが、どうしても毎年毎年今一つ解決に至らない懸案事項があるんです。それは本堂でのご挨拶、お屠蘇振舞をして下さる方がいないのです。何とか毎年私の家族の者と、男性スタッフの方とでやってきましたが、やはり1年で一番おめでたいご挨拶、1番おめでたい縁起物をいただくのに、女性からいただいたほうがありがたいとの要望が強く、解決に至っておりませんでした。頼めばいくらでもお手伝いいただける方があるのですが、それも年越しという大事な家族行事を枉げていただくことになりますから、なかなか声をかけることができません。
いろいろ悩んでおりましたら、近所の女の子が手を挙げてくれました。現在大学生で遠方にお住まいですが、必ず除夜の鐘つきに毎年来てくれる子です。よく聞いてみましたら、今年成人式を迎えるらしく、同級生の友達を何人かつれてお手伝いしていただけることになりました。
こうして本堂には新成人の女の子が3人並び、おめでたい雰囲気が倍増し、寒さも半減致しました。
江戸時代の大俳聖・松尾芭蕉の門下で、俳諧師の服部嵐雪に
梅一輪 一輪ほどの あたたかさ
という句があります。梅の花一輪ごとに暖かい春がやってくる、春が待ち遠しいという意味になろうかと思います。
温泉寺にとりましては、元旦のお手伝いをしてくれた新成人3人の女の子がまさしく梅三輪でありました。極寒の中での除夜の鐘・元旦修正会でしたが、その中で本当に温かい初春を感じました。
新成人としての第1歩を、温泉寺でのお手伝いから始めて下さったことに、住職として本当に感激致しましたし、みんなが喜びました。本当にありがとうございました。この3人様にどうか幸あらんことを念じてやみません。
2011.01.25
散り初めし・・・
先月は温泉寺周辺は紅葉ライトアップで大いに賑わいました。温泉寺にて把握しているだけでも期間中の来場者は約14800人、大型バスも41台という数字が残り、年々賑やかになってきています。要因はやはり入場無料ということと、境内全域が整備されてきたことにあるように思います。前回の茶話でもご紹介しましたように、この行事全てが奉仕により成り立っているおかげです。
現在はあんなに見事だったもみぢも散り、期間中消灯後、毎日のように一緒に飲んだスタッフの方たちとも会えなくなり、少し淋しい感じがします。(結局私が一番楽しんでいたかも・・・)何はともあれ「もみぢ」のおかげで身も心も楽しませてもらいました。
窪田空穂さんに
散り初めし わが庭もみぢ
衰へしものは
静かに美しきかな
という詩があります。
もみぢの葉の最期は、鮮やかな紅葉ですが、その最期(終末)に淋しさを感じつつも、美しいものとすることができるのは、欧米には無い日本人の良さだと思います。
「衰へしものは、静かに美しきかな。」
私はこの部分が大好きです。
温泉寺境内の桜やもみぢを観察していますと、春に芽吹くころも、やはり赤く見えます。新芽自体が赤いのです。葉が成長するに従ってクロロフィルに覆われて鮮やかな緑色の葉になります。これが人間でいう「成人」の状態だと思います。しかし時期が経つとだんだん本来持って生れてきた色に戻っていきます。これが「紅葉」の状態で、たまたまその時期が一生のうちの最期なのだと思います。もみぢの最期は、もともと生れ持っていた本来の色に帰ることだったのです。 新緑の青葉も美しいのですが、やはり本来の色のほうが美しい。
私たち人間にとって、「もともと生れ持っている本来の色・本来の姿」って何でしょう?幼いころの無邪気な姿だというだけでは、あまりにも抽象的すぎですね。
赤ん坊は生後すぐに、誰にも教わらずしておっぱいを飲みます。排泄も上手にします。つまり、「生きたい、生きるんだ」という姿勢を常に見せてくれます。そして少し経つと、「みんなと一緒にいたい」という共生の姿を誰よりも強く見せてくれます。これが私たち人間の本来の姿なんだと思います。みんなと共に生きていくために、
「すみません。」 「ありがとう。」 「あなたどうぞ。」
というたいへん有意義な言葉が存在するのです。これを言えるか言えないかで、ずいぶん人生が変わります。人間でいう「紅葉」の状態は、この三つの言葉を素直に言える時ではないかと思います。
もみぢは決まった時期にしか紅葉できませんが、私たちはいつでも紅葉できますね。だったらまた今度にしようか・・・ではなく、私たちは明日の命も知れぬ無常の身。できるだけ今、この瞬間、紅葉している自分でいたいです。
そう考えるとき、窪田さんの「散り初めし・・・」の詩がより一層感慨深く伝わってきます。
2010.12.03