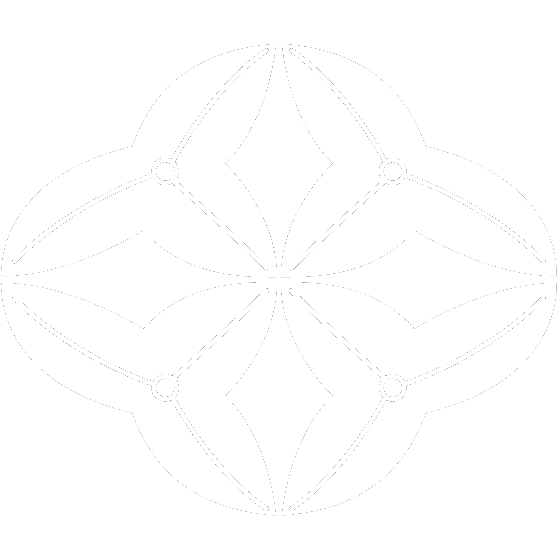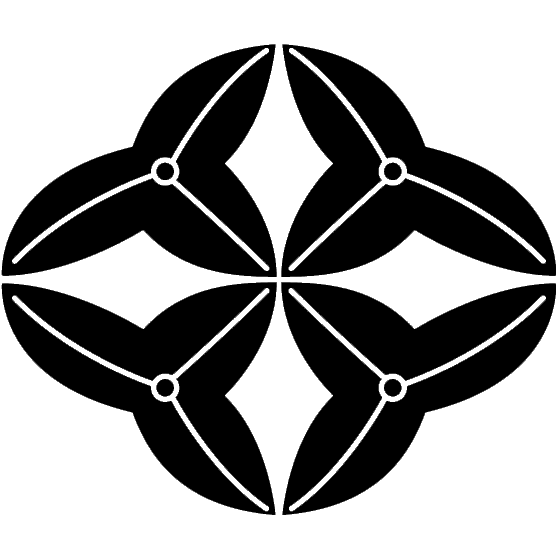
温泉寺茶話
翠の松・白い象さん
下呂へまいりまして9年目の春を迎え、もう梅雨の時期にはいろうとしています。今年は杉や檜の花粉が少なく、所謂アレルギー性鼻炎の私には、とても楽な春でした。(下呂へ来てから花粉症になりました。これだけ周りに杉や檜があれば、当然でしょうが・・・)
やれやれ花粉の季節も終わったな~と、安心していましたが、ここ3日間、また症状が出始めました。原因は松だと思います。松だけは相変わらずの量のようで、私の体調の変化とともに、本堂の机や、吹きさらしの廊下が黄色くなっています。毎朝きれいに拭いても、風のある日は昼ごろには、また黄色くなります。
温泉寺には、モミジや楓、大きく育った杉・檜のほか、シンボルともいうべき松が境内のいたるところに聳え立っています。倒れてきたり、枯れたりするとたいへんなことになってしまいそうな大きな松です。「危ないから切ってしまいたいな~」というのもありますが、本当は「花粉対策に切りたいな~」と思います。ところが、安易に切れない理由もあります。
1つは下呂温泉発祥の縁起「しらさぎ伝説」の松もその中に含まれていること。1265年(文永2年)、山の中の源泉が地震により枯れてしまい、翌年、現在の源泉地、河原の源泉を知らせた白鷺が降り立ったという松。その松の根元に、温泉寺の本尊・薬師瑠璃光如来が鎮座されていたということで、現在も「瑠璃の松」(るりのまつ)という呼び名で親しまれています。しかも、この「瑠璃の松」が一番ややこしい処にそびえていて、他の松を切るのに「危ないから」という理由はつけられません。
もう1つの理由は、温泉寺の所属宗派である臨済宗を確立された、中国の臨済禅師の栽松の因縁があります。臨済禅師は、後人の標榜・つまり後から来る人達の道しるべのために、寺の境内に松を植えられました。それは、実際順路を示すための道しるべでもあり、その寺の年輪でもあり、心の拠り所としての道しるべでもありました。足場が悪く、ゴツゴツとした岩場で、しかも風当たりの強い場所であっても、太く高く、いつでも翠の葉をつけている松。その様相がいつの時代にも共通する不変の真理を示しています。臨済宗の寺に松の木が多くみられるのは、このような因縁によるものです。
温泉寺の歴史を、その容姿にて伝えてくれている松。それと同じように年輪を刻んでいるのが、毎年5月5日(こどもの日)の「はなまつり」に登場する張子の象さんです。約50年前に作られた象さんで、毎年1日だけの登場ですが、頑張って「誕生されたお釈迦様像」を、町内を1周して温泉寺までお連れしてくれています。先導するのは町内の子供たち。みんなでお釈迦様の誕生をお祝いし、仲良く遊ぶことを誓います。
子供たちに人気の象さんですが、今まで50年間、その都度、保護者のお父さんたちの手で補修してもらい、色を塗りなおしてもらいながら、今日に至っております。今の子供たちの親御さんは皆、子供の頃、この象さんを引っ張った方ばかりです。親子二代、もしくは三代に及ぶこの行事、そしてこの象さんも、温泉寺にとっては大切な財産です。
いつかこの象さんも朽ち果ててしまう時がくるかもしれませんが、たとえ象さんの姿が多少変わることがあっても、それを引っ張る子供たちの純粋な瞳だけは、松の葉同様、いつの時代も変わることがありませんように・・・。
2010.05.28
なみだしくや
今さらですが、新年明けましておめでとうございます。
この言葉を申し上げるのに2ヶ月半もかかってしまいました。
ようやく春らしくなり、温泉寺の紅梅も開花しました。
それもそのはず、明日から春のお彼岸です。
というわけで、本日午前中は、仏様にお彼岸団子とお花をお供え致しました。温泉寺では先代和尚さんの時代も手作り団子をお供えしておりました。(たぶんそれまでの和尚さんの時代も・・・)
米粉から団子にして、蒸してお供えするまで、2時間くらいかかります。現在はお彼岸団子もスーパーで買える時代です。買ってくれば、手間も時間も省けます。今までどれだけ買って来ようと思ったことか・・・。
江戸時代の松尾芭蕉「奥の細道」を紐解くと、元禄2年8月14・15日に現在の福井県敦賀市に芭蕉は逗留しています。敦賀には、気比神宮という立派な神社があり、芭蕉も参詣し、句を残しました。
月清し 遊行のもてる 砂の上
奥の細道によると、気比神宮の社殿の前の白砂は、まるで霜を敷き詰めたように白い。その昔、2世他阿上人が一念発起して自ら草を刈り、沼地の境内を乾燥させ、せっせと海岸の白砂を運んでぬかるみを埋めた。その行を、歴代の上人も引き継いで、神殿前には白く輝く砂が敷き詰められている・・・と宿の主人から聞き、深く感激した・・・とあります。
句中の遊行とは、歴代の上人様のことです。当時、白砂をどのような方法で運んだか・・・。などと想像しますと、かなりのご苦労だったことと思います。1日1日少しずつ、地道な作業を1代勤め上げ、更にそのご苦労を、引き継ぐ歴代上人の姿があった。本当に涙ぐましいお話です。
芭蕉は初案の句で、
なみだしくや 遊行のもてる 砂の露
と詠みました。同じことを繰り返し続けていくことは、非常に難しいことです。また、現代の文明の利器による利便性をあえて否定することも、難しいことです。
でも、手間がかかっても、時間をかけてでも同じことを繰り返ししていくことが、日本独自の伝統文化を生み出しました。そこに日本人の良さがあるのではないかと思います。
「お彼岸団子の10個や20個ぐらい、自分でこしらえろ!」
という歴代和尚様の叱咤の声が聞こえてきますが、実はこれも全く当然のことで、特別なことではないと思います。
2010.03.17
子守地蔵様(こもりじぞうさま)
温泉寺の173段の石段下、いわゆる大門の部分に地蔵堂があります。そこのご本尊様は、通称「子守地蔵様」とよばれております。
昔々、飛騨川が氾濫したときに幼い子供と、そのお婆さんが水に流されて亡くなったことを哀れんで、当時の村人が子供の健やかな成長を願ってお祀りしたのが始まりと、伝わっております。
名前と由来の通り、子守地蔵様は幼い子供をしっかり抱いておられます。その子守地蔵様のお祭りを、近所の子供たちと行いました。温泉寺では、その子守地蔵様を大数珠で囲み、みんなで輪になって般若心経をお唱えしながら大数珠を回します。大数珠の上下に、「親玉」とよばれる大きな玉がありますが、それを自分の両親、ご先祖様と思い、親玉が回ってきたら静かに額に当てて、現在ある命と健康に感謝します。更に、これからの成長をお祈りします。
大数珠を回してお祈りする習慣は、京都・百万遍の知恩寺様の百万遍念仏に由来するのだと思いますが、現在でも京都市内の各町内にて行われている地蔵盆(子供のお祭り)の大数珠回しをヒントに、温泉寺では平成16年から始めています。
私は京都の妙心寺でお世話になっていたころ、地蔵盆に何度かお伺いさせてもらい、初めて子供たちが大数珠を回してお地蔵様のお祭りをする姿を目にしました。温泉寺へきてから子守地蔵様の存在を知り、子供行事の一環として始めてみました。
今年で6回目ということもあり、大数珠回しも随分板についてきました。しかも2ヶ月前の夏休みには、毎朝ラジオ体操を温泉寺でやりましたので、その後みんなで本堂にお参りし、毎朝般若心経をお唱えしましたから、今回の大数珠回しは全員が大きな声で般若心経をお唱えしながらできました。子供たちはすっかり般若心経を覚えてしまいました。子供たちの吸収力の高さ、柔軟性に驚きながら、やんちゃしながらも素直に大数珠親玉を額に当てる純粋な瞳に感激してしまいました。
大数珠の真ん中にお座りいただいた「子守地蔵様」、どうかこの子供たちがいつまでも、この純粋な気持ちを忘れませんように!!そして健康な体で育ってくれますように!!
「お祈りやお願い事より、感謝のお参りを!」
と、皆様にいつもはお勧めしている私ですが、この日だけは、ついついお祈り・お願い事をしてしまいました。でも、感謝あっての願い事だから、こういうのもいいでしょう。と、自分に言い聞かせています。
2009.10.23