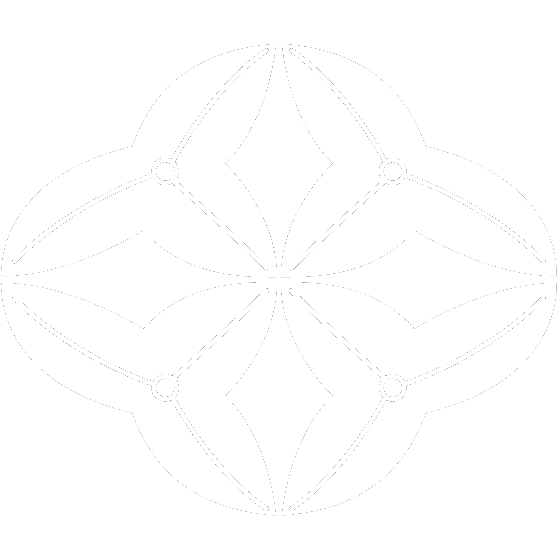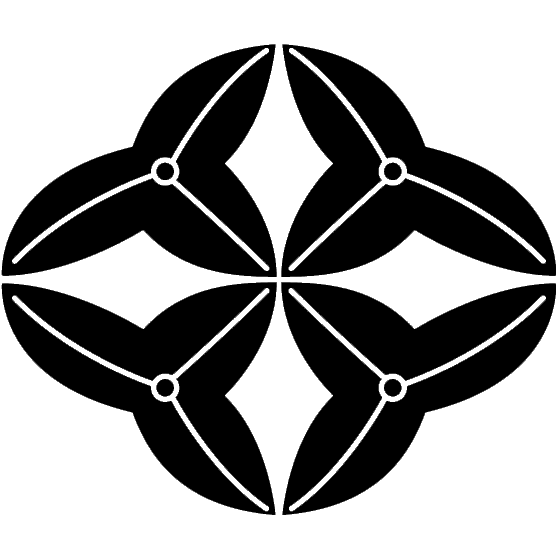
温泉寺茶話
復活!林間学校!!
今年の夏、温泉寺での林間学校が何十年ぶりかに復活しました。
テーマは2つありました。母親のありがたみを改めて知ること、エコロジー重視の生活体験をすること。これを基本の柱に、1泊2日、近所の子供たち22名と私との、林間学校が始まりました。
母親の有難み、家庭の有難みを改めて知るということで、保護者の参加やお手伝いは一切禁止。全て子供たち自身で挑戦してみるという企画。しかもエコロジー重視で。
無謀とささやかれた企画でしたが、成功も失敗も全て良い想い出になるだろうという、極めて楽観的な考え方のもと、まずは本尊様に全員でお参りし、食事作りを始めました。
晩御飯は、季節の野菜の煮物にご飯と味噌汁。プラス漬物。全て炭火を使い、自分たちだけで作ることができました。そのかわり、時間はかかりました。包丁を使えない小さな子は、一生懸命水を汲んできて、お米をといでくれました。お湯を沸かして番茶も作ってくれました。そして野菜以外の唯一のご馳走、油揚げをこんがり焼いてくれました。駄目でもともと、失敗して当たり前という思いでしたが、みんな真剣にやってくれたおかげで、何とかなりました。
「ナス嫌い~。」「ナスだけは勘弁して~。」「漬物はたくあんしか食べれない~。」などと言っていた子も、食事のときはしっかり食べていました。キューリの浅漬け、次の日用に漬けたこうじ味噌漬けも、しっかり食べてくれていました。自分たちで作った料理は、質素でも、見た目が悪くても、やはりおいしいようです。
家庭ではいつでも、お母さんかお婆ちゃんの手により、当たり前のようにご馳走が出てくる。しかも、与えられる量も充分に確保されている。
スイッチを入れれば電気がつく。蛇口をひねれば水が出てくる。これらも当たり前の生活です。
林間学校では、この当たり前ができませんでした。でも、たった1泊2日です。子供たちは逆に、非日常を楽しんでいるようでした。理由は、自分だけではなく、そこにいるみんなが同じ境遇だからです。自然に仲間意識も芽生えたのでしょうか、普段一緒にいることの少ない6年生と1年生の子でも、下は上を慕い、上は下の面倒をみるという姿勢で仲良くやっていました。
釈尊の時代に、このようなお話があります。
あるお金持ちの長者が、大工さんに2階を作るよう頼みました。
大工さんは早速、1階部分の基礎を作り始めます。
ところが長者は突然怒り始め、こう言いました。
「1階はいらん!2階を作れ!!」と。
とんちではありませんが、実際、1階部分がないと2階は存在しないですよね。
思うに、私たちは常に2階のフロアで生活をさせていただいているような気がします。
2階で優雅に暮らすその下、1階部分には誰がいるのでしょうか?
命をつないでくれたご先祖様。育ててくれた両親や恩師。励ましてくれる友達や、ご近所様。また、私たちの活力となる動物や植物の命。などなど・・・。
1階には数え切れないほど、私たちを支えてくれているものがあると思います。その大切な大切な存在に気づくか気づかないかで、2階での生き方が随分変わってきます。
何も知らないまま、2階で安穏と自由気ままに暮らすのか。それとも感謝を知り、自らも1階のフロアに降りてきて誰かのお役に立てるような生き方をするのか。
私には、「こうしなさい!」などと他人様に申し上げる資格もありませんが、私も含め、これから生きていく子供たちには、是非とも後者であって欲しいと願っています。
最後になりましたが、林間学校の食事の後片付け、洗い物を毎回すすんで完璧にこなしてくれた6年生の女の子たち、自分のできることを精一杯努力してくれた1年生から6年生までのみんな、本当にご苦労様でした。おかげで楽しい想い出ができました。ありがとう!!
また、無謀で質素とわかっていながらお子さんを参加させて下さった各御家庭の皆様、慣れない炭火で火傷をしても黙ってくれていた親御さんなど・・・、本当に有難うございました。
2009.08.28
雨の日の花
今日は1日中、雨が降っていました。雨が降ると、いつも思い出す詩があります。
高田敏子さんの「雨の日の花」という詩です。
雨が降っている。
花は咲いている。
花の上におちる雨。
悲しんでいるのは、雨だった。
花をよけて
雨は降ることが、できない。
温泉寺の裏、「楓月庭」のシャクナゲが、雨の降る中、可憐に花を咲かせています。自分がシャクナゲなら、どう思っているだろうか?逆に、自分が雨だったら、どう思っているのだろうか?と考えてしまいます。
きっと、私がシャクナゲなら「痛い!冷たい!雨は少しでいいから、早くやんでくれ!」と叫んでいます。
きっと、私が雨なら「我慢しろ!誰のおかげで生きてると思ってるんだ!」と上から目線で跳ね除けています。
高田さんの詩には、そのどちらでもない、温かさを感じることができます。悲しんでいるのは、雨だったなんて・・・。この視点の違いに、私は強い衝撃を受けたことを今でもよく覚えています。でも、私がシャクナゲなら、この雨の悲しみは理解できていませんでした。ずっと誤解していることでしょう。高田さんの詩は、更にこのように続きます。
花は咲いている。
雨のこころをいたわり、受け止めて
花びらに、雨のこころを光らせて
花は咲いている。
こうして花も、雨の悲しみを理解し、受け止めている。そしてお互いがその存在を認め合い、共存共生している姿は、とてもほほえましい光景だと思います。
考えてみると、私たち人間も、人と人との繋がりの中において、こうして生きていくべきだと思いますが、やはり片方どちらかが誤解してしまうと、たちまち信頼関係は崩れおちていきます。更にもう片方も誤解を生じることとなり、修復不可能な関係になりかねません。
実はこの私も、このような修復不可能な人間関係に陥ってしまったことがあります。しかも、温泉寺にとって非常に大切な方とです。歯車が合わなくなって約1年9ヶ月。この間は非常につらいものでした。相手の方が重い病気を患われ、ついにお会いすることもできなくなりました。しかし相手の方のご親族のご配慮で、先日、ご本人ではありませんでしたが、ご親族の方に、ご無礼とご迷惑に対する謝罪をすることができました。それで相手の方が納得されたとは思いませんし、私自身一生この苦い経験を背負って生きていかなければなりませんが、とにかくこちらは前を向いて歩んでいけるスタンスになったわけです。
だからこそ、高田敏子さんの「雨の日の花」は、私にとって忘れられない詩ですし、決して忘れてはならない詩です。もっと早く、この詩に出会っていれば・・・なんて、あとの祭りなんですけども・・・。
2009.05.17
信心ある処、景観益々美なり。
明けましておめでとうございます。たいへん遅くなりましたが、今年も宜しくお願い致します。
お正月を無事に迎えることができ、今年も皆様方とご一緒に、健康で暮らせるといいなぁ、などと思いながら過ごしているうちに、あっという間に春のお彼岸を迎えてしまいました。
天候が比較的良かったためでしょうか、お正月初詣・お稲荷様の初午祭・春のお彼岸と、例年にないたくさんの参拝者で、年々賑やかになる温泉寺を嬉しく思います。有難うございました。
さて、毎年思うことですが、下呂における春のお彼岸には、いつも1つの変化が見られます。どこが変化するのかと申しますと、お墓にお供えしてあるお花が変化するんです。
最初に申し上げておきますが、温泉寺の173段の石段の両側に広がる墓地は、皆さんそれぞれ熱心にお墓参りされるものですから、年中お花がきれいにお供えしてあります。(住職が温泉寺を自慢できるものの第1位です!)ですから、私を含め、石段を上がってお寺へ来る人達は、本当に気持ちよく石段を上がることができます。観光客の方からも、度々感心する声をお聞きします。
お花の内容は、季節により若干変わり、お正月は松やナンテンが中心。小正月以降は、花筒が凍るため、青木か猫柳が中心です。それが3月のお彼岸前に、ほとんど全てのお墓のお花が、華麗なものに変化するんです。これから以降は、枯花を見ることが滅多にないぐらい、華麗なお花を定期的にお供えされるのです。皆様の、ご先祖様を思う篤い信心が、温泉寺の景観を美しく保っていると言っても、過言ではありません。
更に、1つ注目すべき点があります。温泉寺の墓地内には、勿論無縁となってしまったお墓や、墓守りする方がご遠方にお住まいで、なかなかお墓参りできないという状況のお墓も多々ございます。でも、これらのお墓も、綺麗に守られております。住職も、墓地管理委員会も、救いの手を差し伸べているわけではありません。
実は、これらのお墓も、地元にお住まいの方たちの手によって守られているのです。
例えば、「ここのお爺ちゃんには、生前お世話になった。」とか、
「私の実家の本家だ。」とか、
「私の母が、ここの先々代の爺ちゃん婆ちゃんに育ててもらった。」とか・・・。
理由は様々ですが、ご自分の家のお墓以外にも、きちんとお花を立て、お線香をあげておられるのです。1部の方に限りません。たとえお花を立てることはなくても、静かに手を合わせておられる姿も、度々お見かけします。つまり、ほとんどの方が、自分の家のお墓、他人の家のお墓と一々区別せずに、お世話になった方へ、真心のこもったお墓参りを実行されているのです。ですから、どのお墓を見ても、綺麗に保たれているわけです。(よく、他人のお墓は、触ると良くないという言葉を耳にしますが、温泉寺墓地内に、そのような概念は無さそうです。)
本当に立派な信心であると思います。同時に、住職として感謝しています。
「信心ある処、景観益々美なり。」 です。
温泉寺の本山であります、臨済宗、妙心寺の開山様は、今から650年前に遷化なさる時、お弟子さんに遺言を残されました。その遺言の中に、このような言葉があります。
「前略・・・将来、たとえ私を忘れることはあっても、応灯二祖(私の師匠の大灯国師と、そのまた師匠の大応国師のお二人)の深いご恩を忘れるようなことがあれば、決して私の弟子であるということを許さない。・・・云々・・・」と。
私たちに置き換えて解釈しますと、
「将来、父親の私のことを忘れても、お前のお爺ちゃん、お婆ちゃん、また曾爺ちゃん、曾婆ちゃんのご恩を忘れるようなことがあれば、決して私の子供であるということを許さない!」
と、自分の子供に向かって言っているということです。
なかなか言える言葉ではないですよねぇ。私自身、自分の子供にまだ言えません。それどころか、逆に「誰のおかげで生きてると思ってるんだ!」と、子供に言ってしまいそうです。
でも、今現在、温泉寺の墓地内にお墓を持つ方たちの親御さん達は、かつて自分の子供たちに開山様と同じようなことを伝え、諭してきたのではないかと思います。綺麗に保たれている墓地は、その立派な教育の賜物ではないかと思います。
前にも記述しましたが、前述の墓地内は勿論、石段掃除の奉仕をして下さったり、境内の掃除・建物内の掃除を奉仕して下さる方が、温泉寺にはたくさん見えます。その方たちに、奉仕をする明確な理由なんて無いのではないかと思います。その証拠に、奉仕に対する物質的・精神的な対価が、お寺から一切還元されていないからです。(すみません・・・。)
ということは、皆さんがそれぞれにお持ちになっている広大な信心と、慈悲心による行為であると、私は認識し、頭が下がるのです。その広大な信心・慈悲心を、「仏心」とよび、そこから生まれる報恩の行・つまり奉仕という形で現れる姿を「禅」とよんでいるのです。妙心寺の開山様の遺言は、今まさに、温泉寺のまわりで実行されております。それも地元の方たちの手で。
「信心ある処、景観益々美なり。」
しつこいようですが、この言葉、実はこの不肖坊主が勝手に作った言葉です。温泉寺を見ていると、本当にそう思うからです。なにしろ、境内の中で一番汚い所と言えば、間違いなく住職の守るべき、「歴代祖師のお墓」(歴代の和尚様のお墓)だからです。わかってはいますが、相変わらず汚いということは、住職自身の内容の問題です。明日、妙心寺へ、開山様の650年法要のお参りに出かけます。朝、きちんと お墓にお参りしてから出発しようと思います。
2009.03.26