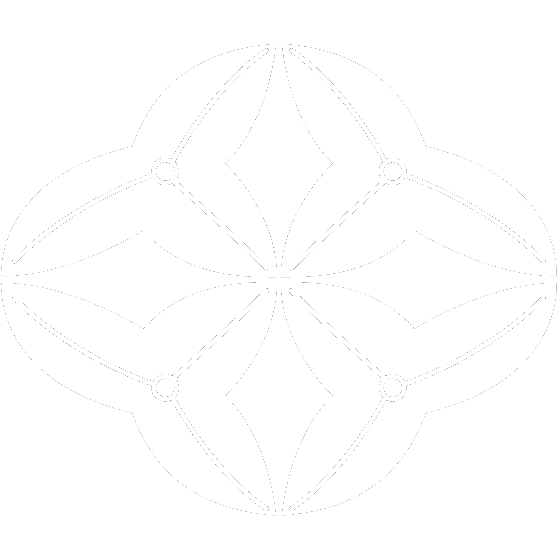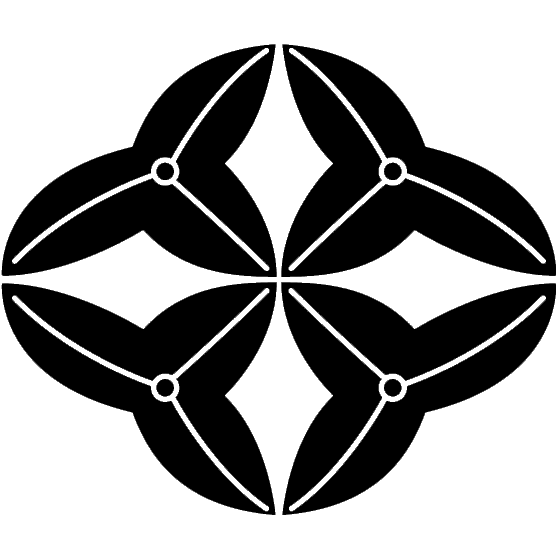
温泉寺茶話
お釈迦様のご遺言~自燈明~
本日2月15日は、仏教を始められたお釈迦様のご命日です。
お釈迦様は入滅(お亡くなりになること)の際、長年常に寝食を共にしてきた弟子のアーナンダに、お釈迦様亡きあと、自分は何を頼って生きていけばいいのかを涙ながらに尋ねられます。
そこでお釈迦様がお示しになった、言わばご遺言が次のお言葉です。
【自らを拠りどころとし、法を拠りどころとせよ】
“自燈明法燈明”の教えです。
お釈迦様は、「私の教えをよく覚えておいて、それに従いなさい」とも、「私の教えをよく書きとどめておいて、それに従いなさい」とも仰いませんでした。
【あなたという自分自身を拠りどころとし、生まれた時のままの素直な自分を拠りどころとして生きなさい】(個人的な意訳です)
と、仰いました。肝心な時の寄る辺は自分自身だと。そして自分自身とは、勝手な自我や経験によって作り上げられた先入観・偏見を離れた、生まれた時のままの本来の自分なのだと。
先日、地元の中学生ベースボールクラブの子供さんが坐禅研修にみえました。例えば、1点差で勝っている試合の最終回、2アウトなんだけれども満塁のピンチの場面、相手が打っても、こちらがミスをしても“サヨナラ負け”のリスクを背負った場面です。投手も野手も、できれば打たれたくないし、ミスもしたくない。その時に、
“自分のところにボールが飛んで来たら嫌だな~” とか、
“どうか自分以外の野手のところに打ってくれ~” などと思いながら守るのか、それとも
“是非自分がボールをさばいてアウトを取って勝つんだ”
と自分を信じて守るのかでは、体の反応も動きも大きく変わってくると思います。
そんなことを話しながら、どうか自分自身を信じる力を養ってほしいと、子供たちは全員真剣に坐禅に取り組んでくれました。
今後のチームのご活躍ご健闘をお祈りしております。

(地元ベースボールクラブの坐禅研修)

(坐禅後は、173段の石段トレーニング)これも坐禅研修のプログラムです(笑)

掃除もバッチリ! ありがとうございました!

数日後、地元高校生の皆さんが坐禅に挑戦!

さすがに姿勢が良い!
この後、写経も挑戦してくださいました。
2019.02.15
1年間ご無事でありますように

(2018年12月31日 除夜の鐘)

(除夜の鐘 開始5分前)
たくさんのご参詣をいただき、有難かったのですが、寒い中お並びいただくことになりました。本当にありがとうございました。
謹賀新年 今年もよろしくお願い申し上げます。
昨年大晦日、「平成」最後の除夜の鐘・新年修正会を厳修致しました。大勢のご参詣をいただき、ありがとうございました。
まずは本堂にお参りいただき、新成人の皆さんより新年の縁起物のお屠蘇、干支の色紙をお受けいただいた後に、鐘を撞いていただきます。
住職はその間、大般若理趣分をお唱えし、皆様方の1年間の「無事」を祈ります。引続き、祝聖を修めて国家安泰を願います。
さて、昨年は・・・、と言うよりは昨年も、全国各地で災害の多い年でした。下呂温泉も少なからず災害の影響を直接的に受けました。でありますから余計に思うのですが、「無事」以上の幸せは無いと思うのであります。心から皆様方の「無事」をお祈り申し上げます。
ところで、私たちの宗門「臨済宗」の宗祖、中国の臨済禅師も私達の「無事」を願って下さっております。
【無事是れ貴人 ただ造作することなかれ】(臨済録)
「無事」こそ貴い人であると仰っているのです。
ただし、“造作することなかれ” と忠告もされています。
つまり、私たちの心の中にある“計らい”、或いは“企み”と言う造作のないところが「無事」であり、貴い人だと仰っているのです。
臨済禅師は私たちの肉体的な「無事」だけではなく、「心の無事」をも願っておられるのです。
私が温泉寺の住職を任されて間もないころ、前任者であった先住職の老僧さんから、草取りについてよく叱られました。私は草が生えているのがわかっていても、いちいち草取りにいそしむことはなく、行事前やお客様がお越しになるのがわかっている日の直前にしか草取りをしませんでした。事実、毎日毎日少しづつ草を取っていても、またすぐに草は生えてきます。だから、行事をする日の直前に一気に草を取ってきれいにしました。
ですが、先住職はそのやり方が気に召さなかったようです。ただ単に私の“なまけ心”を叱るのではなく、私の心の中にある「行事前に一気に草を取ったほうが効率的で、しかも完全にきれいになり、お客様からも評価が高いものになるだろう」という“計らいの心”、“企てる心”を叱られたのです。
そして先住職は若い私にこのように教示して下さいました。
「何故草を取るのかって? それは草が生えるからだよ! それ以外に理由は無い!」 と。
当時、「境内をきれいに保つことで、檀家さんなどのお客様から自分への評価を得たい」と、心の中で求めていた自分がとても恥ずかしく、同時に情けなくなったことを覚えています。
臨済禅師も
【求心やむところ、即ち無事】(臨済録)
他に求める心がなくなったところが、そのまま「無事の人」だと念を押されます。
他人からの高評価を求めてしまうが故に企て、計らい、その結果自分自身が悩み、苦しむことになるのです。今でも私はこういうことになる場合があります。だから気を引き締めて、心も体も「無事」で居れますように精進したいと思います。

(除夜の鐘・修正会祈祷)

(お屠蘇と干支色紙は地元の新成人の方よりお受けいただきます)
2019.02.14
年の暮れ
元禄六年(1693年)、松尾芭蕉50歳の時
盗人に 逢うた夜もあり 年の暮れ (続猿蓑より)
を観ることができます。住居にほとんど金品は無かっただろうと想像しますが、それでも意外なことに盗人に入られて・・・
でも何とか無事に新年を迎えることができそうだという俳句でありましょう。
1年を振り返ると、盗人でなくとも、思いもよらない出来事がたくさんありました。そういうことにその都度心を揺れ動かし、バタバタと1年が過ぎてきたような気がします。
有難いことに私の場合、盗人だらけの1年間だったとしても、そのたびに多くの皆様のご援助を受けてまいりました。本当にありがとうございました。
また来たる2018年も、何卒よろしくお願い申し上げます。
ただ、「盗人」を自分の心の中の勝手な欲望とか、つまらないわだかまりというふうに置き換えると・・・
これもまた盗人だらけの1年だったように思います。
住職も要反省ですm(. .)m


春と秋はいろいろな方が坐禅に挑戦!

地元こども園の園児も頑張りました。

今年のライトアップ。
詩人書家・小林勇輝さんの「言葉の結晶展」も大反響をよびました。

足湯は下呂温泉事業協同組合様・旅館組合様のご協力によるもの。
誠にありがとうございました。
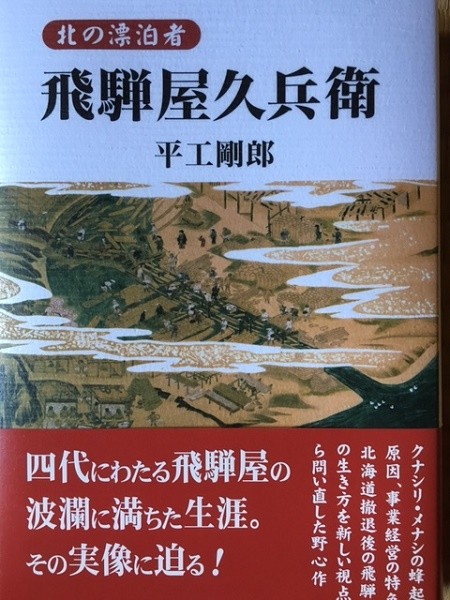
温泉寺開基・武川家子孫で江戸時代に活躍した飛騨屋4代の壮絶な物語。
詳細な資料により新事実も数々発見されました。
著者・平工先生による出版記念講演も開催でき、改めて先人のご苦労と見識を知ることができました。
2017.12.20