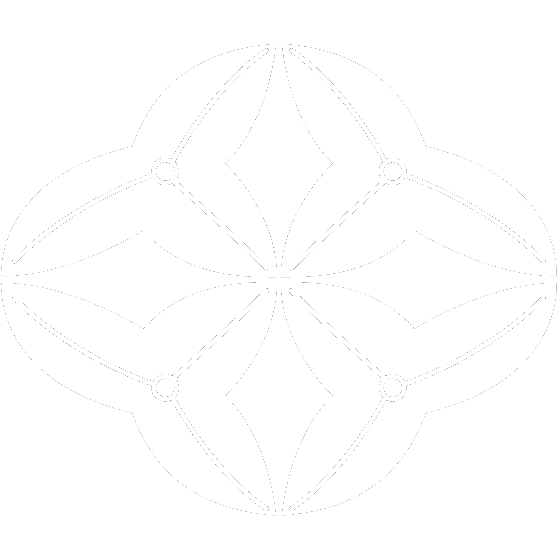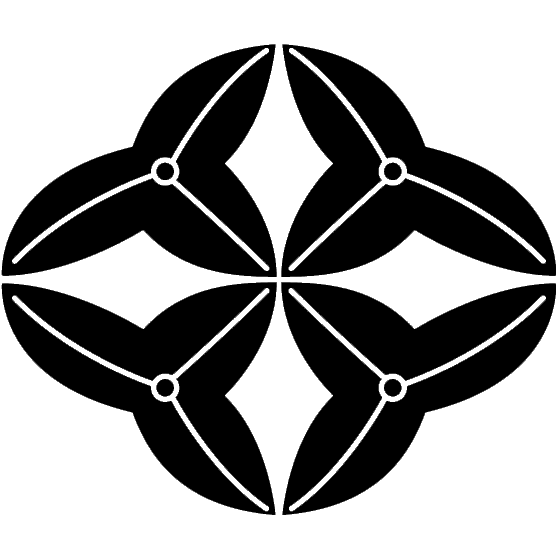
温泉寺茶話
I Love 下呂温泉!
今月末で、温泉寺に来てまる五年が経ちます。その間、地元の皆さんの支えのおかげで逃げ出しもせずに居れたことは、言うまでもありません。感謝しています。
学生時代を含め、足掛け九年いた京都時代に最もお世話になった妙心寺天授院の老師には、「ここにいた時間の倍の時間は、我慢せよ。」などと言われて下呂に送り込まれたわけですが、我慢どころか、あたかも以前から下呂にいたような図々しい自分の態度を反省しています。
寄り道とお酒を好んだ風来坊・種田山頭火は、私の尊敬する僧侶の一人ですが、(尊敬できない部分もありますが・・・)最も尊敬する点は、いつでも人間的な純粋さを忘れなかったという点です。とりあえず表向きだけでも「一般的な坊主」を演出していれば、檀家制度の上に生活を保障された寺の住職として安穏と暮らせたはずなのに、どうしても自分の本心に嘘がつけず、放浪するしかない羽目になりました。家も金も食べる物も何も無い、そんなその日暮の中、絶対に手放さなかった物は、母親の位牌だったそうです。何だか忘れていたことを、思い出させてくれるような気がします。
世の中で一番かわいいと思っている「自分」が、実は一番情けないものであると悟ったがために、心の中でもがき苦しんだ山頭火が出した結論は、
「道は前にある。まっすぐに行こう。」
という答えでした。
私も寄り道が大好きな人間ですが、自分が進むべき方向を忘れずに進みたいと思います。たまに方向を見失う場合もありますので、その都度ご注意いただきたいと存じます。今後とも温泉寺護持のため、ご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。
2007.03.06
禅僧・ラルフ道人
1月7日、一人の禅者がこの世を去りました。彼はドイツ人で「ラルフ・フースラーゲ」という名の居士です。自国で教職をしながら、日本で出家した方です。
私は12年前、学生専用の禅堂で初めてラルフ師と出会いました。それは私にとってまさに衝撃的な出会いでした。当時はそんなに衝撃的な出会いだとは思いませんでしたが、私のその後の人生(修行過程)において大きな影響を与えたことは間違いありません。
見かけはただのデカイおじさんです。やることも非常に自分勝手で、禅堂暮らしの中では一人だけ、とても気楽そうな感じがしました。まだ学生だった私達は、時間に追われ、規律に追われ、ヒーヒー言ってましたが、何の手助けもしてくれず、ただ一人自分のことだけをのんびりやるような方でした。「本当にドイツでは先生なのか?この人に教えられている子供はどんな生徒なんだろう?」と思ってしまうほど、お気楽な方でした。
ただ、人に迷惑をかけるということは一切ありませんでしたし、とてもユニークで、人を笑わせるのが得意な方でした。ラルフ師のそばで怒っている人を見たことがありません。他人を誰でも分け隔てなく受け入れる姿勢は、見習うべき点だと当時から思っていました。
そして何よりも道心の深さに感銘しました。坐禅や読経、作務(掃除)などという当たり前なことは勿論ですが、ラルフ師の素晴しいところは、禅堂内でもプライベートでも食事は質素、酒は少量、贅沢もせず、必要以上に物を求めず、ただあるがままを受け入れていたというところです。特に釈尊のおっしゃった戒律を、執着するように頑なに守っていたようなこともなく、戒律に従った生活が普通に、自然な感じでありました。だから少しも偉そうな態度も無く、自分を他人にアピールするようなこともありませんでした。それでいて自分の中には何でも受け入れることができる、まさに外に求めず、内に求める坐禅がそのまま師の生活スタイルだったのです。私が何度もドイツに訪れたり、何週間も日本で一緒に過ごした結果、最初に抱いていた自分勝手だというイメージは間違いで、実はありのままに満足し、何にでも同化していける禅特有の自由な境涯の持ち主だったと思います。自他不二の世界です。(ただ、何にでも同化しちゃうから、そばにいる人にとっては、やはり自分勝手だと思われますけど・・・。)
そんなラルフ師の姿は、坊主の道を歩んだ私には、とても大きな存在でした。学生の立場から本格的な修行僧になって五年経っても、温泉寺に来てまた住職として五年経った今でも、相変わらずどころか益々煩悩は増えていくばかり。偉そうな態度、偉そうに見せる要領の良さ、不飲酒戒は破りっぱなし。でも、ラルフ師が本来の禅坊主の姿を私の目に焼き付けてくれたおかげで、今、自分が何とか禅坊主をさせていただいているのだと思います。
このページの一番上の写真は、ラルフ師が亡くなる半年前に、私にくれた写真です。英語で書かれた手紙の内容を十分理解できませんでしたが、どうやら旅行の車窓から撮影したもののようです。今までたくさん写真をもらいましたが、この写真が一番好きです。広大な花畑にポツンと木が一本。とても大きな木ですが、威張っているような感じは全く無く、むしろ小さな花達と一緒に何か歌でも歌っているような感じがします。気取らず、飾らず、自然に花畑に溶け込んでいる巨大な一本の木は、何だか禅堂の学生の中に普通に溶け込んでいたラルフ師を彷彿とさせ、あるがままを受け入れる彼の人生を思わせ、同時に禅僧の在り方を教えてくれているようです。この写真をカメラに納めた時、間違いなく死を間近に感じていたと思いますが、果たしてラルフ師はどんな思いでこの光景を眺めていたのでしょう?その時の気持ちを察することはできませんが、形見だと思って部屋に暫く飾っておこうと思います。
今はラルフ師の58年間の人生の一部を、少しでも一緒に過ごさせていただいたことにただ感謝しています。ご冥福をお祈りしています。
2007.02.10
続・行く年来る年(反省文)
皆様、明けましておめでとうございます。今年も懲りずにお付き合いいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
新年を迎えてようやく落ち着いたと思ったら、あっという間に今日は小正月です(本当は旧暦の1月15日)。小正月には、一年の健康を願って「小豆粥」を食べる習慣がありますね。小正月に対して大正月の元旦の頃は、何かと正月行事で慌しく、本当に心から正月らしく落ち着いて過ごせるのが、意外に小正月だったりします。
暮れから新年にかけて、今年の意気込みを前回の茶話でお話しましたが、言ったはいいものの、実行できるかどうか不安要素たっぷりの抱負でした。自信たっぷりの抱負なら、今年も1年力強く生きていけそうな気がしますが、そうではないのでたいへん気の重い年越しでした。しかしそんな私にとって、とても勇気づけてくれる本を、ある方が紹介してくれました。短いお話ですが、とても考えさせられるお話です。南米アンデス地方に伝わるお話だそうです。
「ハチドリのひとしずく」 (監修・辻信一、光文社)
森が燃えていました。
森の生き物たちは、われ先にと
逃げていきました。
でもクリキンディという名の
ハチドリだけは
いったりきたり
くちばしで 水のしずくを
一滴ずつ運んでは
火の上に 落としていきます。
動物たちが それを見て
「そんなことをして
いったい何になるんだ。」
といって笑います。
クリキンディは こう答えました。
「私は 私にできることをしているだけ。」
以上(注・ハチドリとは、中南米と北米に棲息する、体長10センチ前後の鳥)
私は自分の中に、ある種「あきらめ」のような物を自分自身に感じていましたが、このハチドリに出会って、改めて気の引き締まる思いがしました。「自分が変わる」だなんて、到底無理。だから「子供が変わる」「明日が変わる」だなんて、なおさら無理。と決め付けていました。それはまるで、さっきのお話の中の、ハチドリを見て笑っていた動物たちの如きです。
そうではなく、何でもいいから、自分のできることを少しずつ少しずつ、地道にやっていくことが大切なんだと、教えられました。「そんなことをしたって。」と笑われるようなことでもいいから、すごくスローペースでもいいから、これから生きていく子供達のために、自分ができることを精一杯やろうと思いました。
江戸時代の高僧・白隠禅師の著書「毒語心経」に
「徳雲の閑古錐 (とくうんの かんこすい)
幾たびか妙峰頂を下る (いくたびか みょうぶちょうをくだる)
他の痴聖人を傭って (たの ちせいじんを やとって)
雪を担って共に井を塡む (ゆきをになって ともにせいをうずむ)」
という一節があります。徳雲というお坊さんは、使い古して先の丸まった錐のように、悟り臭くない本当の禅の境涯の持ち主で、妙峰山という山の頂に住んでいましたが、愚かなほどに正直な人を雇っては、二人でせっせと雪を運んで、井戸を埋めようとしていたというお話です。これも一見馬鹿らしく、無駄な行為そのものなのですが、少しでも少しでもと、ひたすら精進・努力する姿は、菩薩さんそのものです。
南米アンデス地方の先人たちも、我が臨済宗の祖師も、共にあきらめず、何でもないようなことでも疎かにせずに、自分にできることを精一杯続けることの大切さを教えてくれています。
だから私も、何年かかるか何十年かかるかわかりませんが、今、自分にできることを地道に続けていこうと思います。そのうちに、後になってそれが子供達の成長過程において、少しでも良い結果につながれば言うこと無しです。
今年もご指導、ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。
2007.01.15