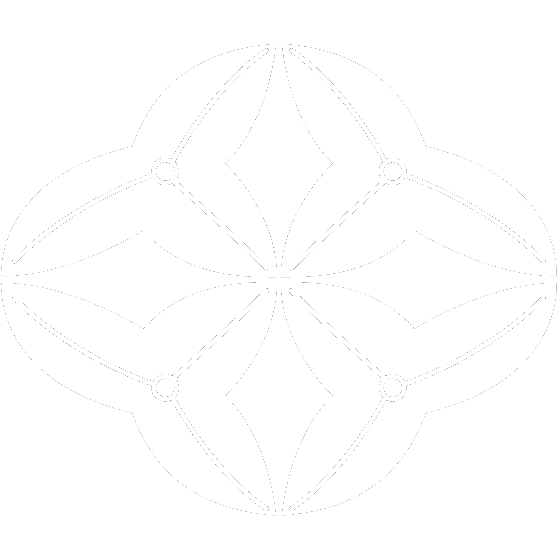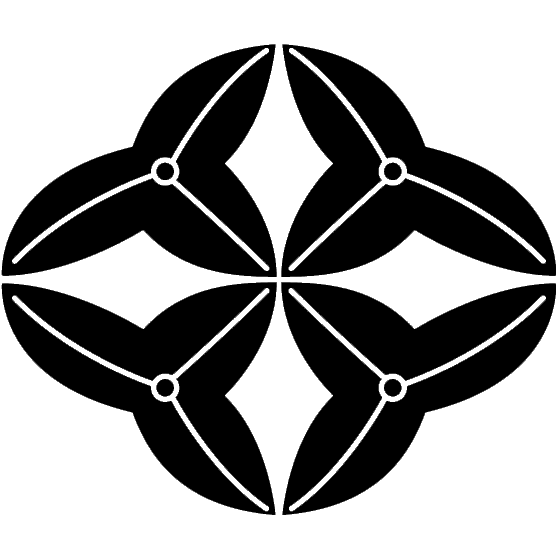
温泉寺茶話
お月さんとウサギさん
こんにちは。日毎に朝晩の冷え込みが増し、日暮れの時間も早くなってまいりました。秋の訪れを感じます。
前々回の茶話でお話しましたとおり、私自身暴飲暴食に気をつけなければと思いつつ、「食欲の秋!」と言わんばかりに秋の実りを楽しんでいます。きのこ類、里芋、栗など、本当に山の幸は一杯飲むのにうってつけの肴になります。いろいろな方から旬の物をいただき、感謝しています。
他にも秋と言えば「読書の秋」「スポーツの秋」など、何をしていても心地良いのが今頃の季節なんでしょうね。
そういえば今月6日は仲秋の名月でした。例年は9月のお彼岸頃ですが、今年は10月に入ってからの名月となりました。所謂旧暦の8月15日のお月さんですね。温泉寺でもすすきや萩を花瓶に活けて、里芋と月見団子をお供えし、秋の風情を楽しみました。京都の専門道場時代は、この日の晩は、本堂の縁側にこっそり湯のみと一升瓶を持ってきて、ほろ酔いの中、坐禅してました。「花より団子」ならぬ「月より一杯」という感じでした。でも当時は楽しみと言えばそのぐらいの程度しかなかったので、仲秋の名月は楽しみでした。ばれないように「こっそり」飲むのがまたいいんですよね。
という訳で、まったくこれまで「お月さん」のことに特に興味を持っていた訳ではないですが、幼心にお月さんと言えば、「ウサギが餅をついている」というイメージは何故だかありました。中国でも月のことを「玉兎」(ぎょくと)と表現しますが、お月さんと兎は深い関わりがあるようです。
では兎とはどんな動物なのでしょうか。お釈迦様の前世を描いた「ジャータカ」と呼ばれる書物にこんな逸話が出てきます。
ある日、森の動物達が仲良く遊んでいました。そこに今にも死にそうな一人のおじいさんがやって来ました。おじいさんは動物達に、「何か食べるものを恵んで下さい。」と頼みます。動物達は普段から善行を心がけていたので、すぐに食べ物を探しに行きました。鳥は空を飛び、川で魚を捕まえました。猿は木立を駆け巡り、あっという間に木の実をたくさん集めました。猪は大地を駆け回り、竹の子や芋を掘り出しました。みんなそれぞれに、食べる物をおじいさんに差し出しました。しかし兎だけが一人、何もできずにいました。自分は何も差し上げる物が無い。そう思った兎は、一生懸命野原を駆け巡り、枯れ枝をたくさん集めて来ました。キョトンと見ていた仲間やおじいさんの目の前で、兎は枯れ枝に火をつけて、「私には何も差し上げる物がありませんから、どうぞ私の肉を召し上がって下さい。」と言い残し、なんと火の中に自分の身を投げたのです。その瞬間、死にそうなおじいさんが帝釈天の姿に変わり、兎の命を救い、その心(仏心・慈悲の心)を褒め称えました。というお話です。
お月さんは太陽とは対照的で、その光も柔らかく、女性的で慈悲心の象徴です。そのお月さんと、慈悲深い兎は一心同体なんですね。ですから「お月さんで兎が餅をついている。」という発想は、平和の象徴なんです。古来より、先人達は仲秋の名月に兎を思い、平和な世の中を願ったに違いありません。
温泉寺で雲の隙間から姿を見せた名月を見て、我が子は何を感じたのだろうと、よっぽど聞きたかったのですが、若干反抗期なのでやめときました。その後、街では有志が集まり、「ギスギスした社会にゆとりを持とう」というキャッチフレーズのもと、仲秋の名月を愛でる宴が催されました。勿論私も喜んで参加させていただき、少し肌寒さを感じる中、あったか~いお酒をいただきました。名月さん、ウサギさん、ご馳走様でした。
2006.10.23
クモの糸
こんにちは。1ヶ月に最低2回はこのページを更新しようと思ってますが、早くも10月に突入し、先月も結局目標達成はなりませんでした。なかなか軌道にのらないということが、温泉寺のホームページそのもののイメージになってしまっています。
さて、話は1週間前、まだ秋のお彼岸の真っ只中です。24日(日)に、近所の子供達と大数珠をまわしました。これは例えば京都市内の各地域で今も行われている地蔵盆のようなものです。室町時代、京都で疫病が大流行した際、百万遍念仏をこの大数珠を使って唱えたところ、パタッと疫病が治まったことから、京の都の方達は、今でも8月下旬に各地域のお地蔵さんを囲み、大数珠をまわすのです。(京都市左京区百万遍という地名は、実はここに由来します。確か、百万遍には念仏寺というお寺もあると思います。)そこで我が飛騨地方には、江戸時代中期の高僧・白隠禅師がこの大数珠まわし(地元では数珠繰りと呼ばれています)を伝えました。
温泉寺には、境内に続く173段の石段の下に、「子守地蔵堂」があります。子守地蔵だなんて、初めて耳にされる方も多いと思いますが、これはやはり江戸時代、飛騨川の大氾濫により濁流に飲み込まれ、命を落とした老婆と幼子の霊を慰めるために祀られたお地蔵さんです。このお地蔵さんの功徳を、近所の子供達と分かち合い、健やかな成長を願おうと、一昨年から秋のお彼岸の行事として「子守地蔵大数珠繰り」を始めました。(今まで温泉寺では数珠繰りの実績が全く無く、当然大数珠もありませんでしたから、一昨年、昨年は他所から大数珠をお借りしていたのです。しかし今年に入って、子供達のためにと、地元の建具師・今井頼雄様が新品の大数珠を寄贈して下さいました。感謝しています。)
お地蔵さんと言えば、冥界の裁判官・閻魔大王を連想します。私達は死後、この閻魔大王により極楽行きか、地獄行きかを分けられます。この閻魔大王こそ、実はお地蔵さんの化身なので、亡者の35日目(五七日忌・閻魔大王の裁判の日)には遺族の方は、懸命にお地蔵さんへお参りされます。しかし最近はこのような風習もなくなり、子供達に地獄や極楽などと言っても「和尚さん、地獄や極楽を自分の目で見たことあるの?」とか、「そんなに言うなら閻魔をここに連れて来てよ!」とかいうセリフと冷ややかな眼差しが返ってきます。
う~~ん。コイツラにお地蔵さんについて何を喋ろうかと、数珠繰り当日まで考えました。やはり先人は偉大です。芥川龍之介の「クモの糸」の話をしました。小学生にも理解しやすく、予想以上にこちらの話に釘づけでした。大成功!!ハッハッハッ!
昔、盗賊グループの親分がいました。たくさんの人達の物を盗んだり、脅し取ったりしていたから、バチが当たって地獄へ落ちました。子分も全員地獄へ落ちました。地獄で苦しんでいる親分を見た、天国のお釈迦様が、ある日、生前の親分の行動に一つだけ良い行動があったのを思い出しました。それは、親分が歩いていた道に一匹のクモがいて、親分は普通なら踏みつけても平気なんだけど、たまたまその時は「おっと、危ない」と言って、クモをわざと避けて歩いたことが一度だけあったのです。クモの命を粗末にしなかったということで、お釈迦様は天国から地獄にいる親分の所まで、一本のクモの糸を垂らしました。親分は「これで天国に行ける。苦しみから解放される。」と大喜びして、クモの糸をどんどん上って行きました。ところが、下を見下ろすと、大勢の子分達も上ってきます。われ先にと、すごい勢いで上ってきます。親分はすかさずクモの糸が切れてしまうことを恐れて、「このクモの糸は、俺だけのものだ!お前らは来るな!」と大声で叫びました。するとその瞬間、クモの糸がプツッと切れ、親分も子分もみんな地獄へ再び落ちて行きました。・・・というお話です。(かなり略してあります。ご容赦下さい。)
さて、この話を聞いた子供達に「どうして最後にクモの糸が切れてしまったのか?」 「どうすれば親分は地獄へ落ちずに、天国へ行くことができたか?」ということを尋ねてみました。良かったです。みんなほぼ理解をしてくれていました。「みんなで一緒に天国へ行こう!!」と親分が言っていたら、きっと全員天国へ行けたはずだと、みんなが結論を出してくれました。
この言葉を現世の自分達に置き換えると、「みんなで一緒に幸せになりましょう!!」という言葉になります。これは般若心経の「ギャーテー ギャーテー ハーラー ギャーテー ハラソウギャーテー ボージー ソワカ。」という有名な最後の一句そのものです。これで子供達にも若干般若心経が理解できたかな・・・?
何はともあれ、子守地蔵さんを大数珠で輪になって囲み、和でもって一心にまわす子供達の姿に、何だか久しぶりの微笑ましさを感じました。それと私だけ、生意気な子供達への法話がうまくいき、変な安堵の汗をかいていました。来年はどうしよう・・・と思いながら。(芥川先生、有難う!)
2006.10.02
山頭火の気持ち
暫くご無沙汰してました。当山のHPのこのつまらない茶飲み話も、おかげ様で目を通して下さる方があり、「HPを見て来ました」と言って旅行がてら先祖供養や水子供養をなさったり、「まだ更新しないのか!!」と尻をたたいて下さったりで、有難く思っています。
8月は本当に暑かったですねぇ。その上、お盆行事その他雑用に追われ、いつの間にか9月に入っていました。さぁ、また気持ち新たに頑張るぞ!と思いきや、最初からズッコケました。生まれて初めて救急車に乗せていただいたのです。(地元の皆さんにはたいへんご心配をおかけしました。もう大丈夫です。)結局、食塩水のようなものを点滴してもらって、数時間後、寺に帰りました。(皆様、暑い時期は適度な水分と塩分の補給を心がけましょう!ちなみにビールなどは、水分補給の足しにはならないそうです。)
とまあそんな訳で無事、寺に帰ることができましたが、病院に運ばれてからはいろいろな検査をして、その後、病室に一人ポツンと寝ていました。
「忙しい」「慌しい」「あれもこれもやらんならん」と、気張っていた寺が、随分遠くに感じ、
「やっぱり一人がよろしい 雑草」(山頭火)
と、一人静かに休める空間が心地よい感じがしました。
しかしそれもつかの間。よく考えてみると、約束していた法事が30分後に迫っている。すでに今日の月命日のお参りは、無断欠勤になっている。さぁどうしよう!?と、急に心穏やかではなくなりました。携帯電話も無く、そもそもベッドから起き上がれない状態で、どうやって外部と連絡を取ったらいいのかと思うと、何だか寂しい感じがしました。
「やっぱり一人はさみしい 枯れ草」(山頭火)
今の自分は、世の中にはおろか、自分のことさえも満足にできない、まるで枯れ草みたいなもんだなぁ。
「どうしようもない私が 歩いている。」(山頭火)
という状態でした。約束も仕事も成し遂げることができない情けなさ。
すっかり悲観的になっていた私を救ってくれたのは、地元ネットワークの速さでした。早速話を聞いた下呂の私の身元引受人様(坊主の世界では案下所といいます。)と友人が駆けつけてくれたのです。外部との連絡や段取り、必需品もそろえてもらいました。助かりました。どうでもいい会話も、この時だけは、何だか有難く思えました。一言「飲みすぎだ!」と片付けられましたが、そばに誰かがいるという安心感は、たとえようの無いほど心強いものです。
ちなみにこの後、酒屋さんと、なんと法事の約束を果たせなかった先の煙草屋さんまで駆けつけて下さり、お互いに「うちの酒は悪くない。」「うちの煙草も悪くない。」という結果に納まりました。要は自己責任ですね。
このように皆様にご心配とご迷惑をおかけしたのですが、それにも関わらずさらに皆様のお蔭で自分の進むべき道を歩ませてもらう幸せを感じています。たまには反省して、自分の尻は自分でふけるようにならなきゃ駄目だなぁと思います。
「道は前にある。
まっすぐ行こう。」(山頭火)
◎種田山頭火(明治15年~昭和15年)
山口県防府市出身。大地主の息子。11歳の時、母が自殺。早稲田大学文学部へ入学するも、神経衰弱のため中退。帰省し家業の造り酒屋を手伝うも、父親の放蕩と自分の酒癖のため破産。妻子と共に九州へ赴くが、離婚。その後、熊本市、報恩寺・望月義庵に自殺未遂を助けられ、出家得度。大正15年より行脚に出かけ、多くの自由律俳句を詠む。山頭火は荻原井泉水の門下生で、尾崎放哉と並び称される。昭和15年、松山市「一草庵」にて57歳で生涯を閉じる。
2006.09.06