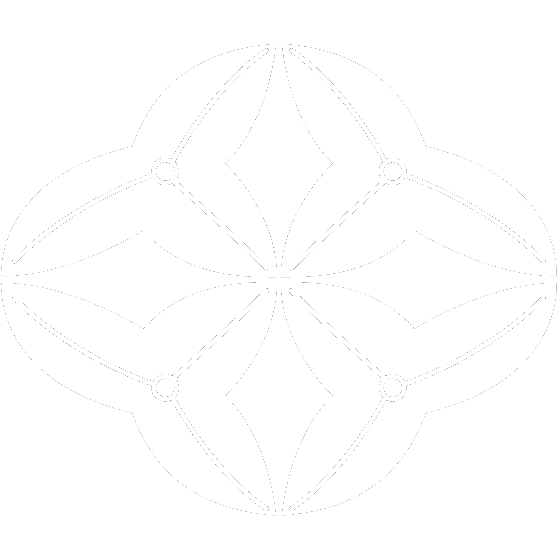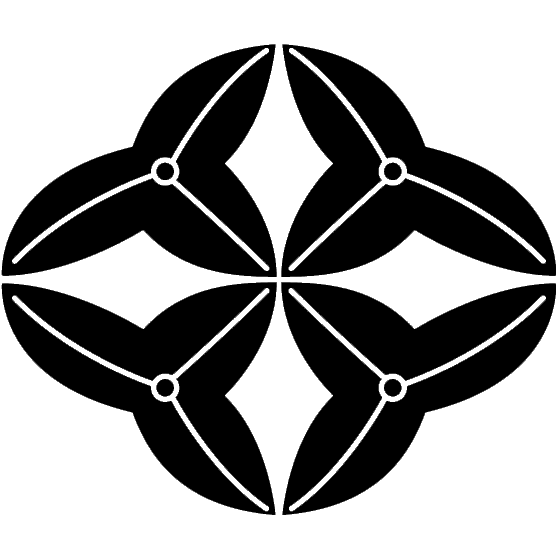
温泉寺茶話
色メガネ
しばらく寺を留守にしていましたので、たいへん久しぶりに更新します。帰りましてから早速、去る6月7日(水)に下呂温泉の企業に今春就職されました新入社員さん達と一緒に坐禅研修を行いました。午前中は坐禅、禅家作法による昼食(斎座)の後、午後は京都・嵐山・天龍寺国際禅堂師家・安永祖堂老師(現在花園大学教授・松雲寺住職)をお招きして、講演を聴きました。高校を卒業したばかりの若い方と一緒に坐禅をできたことは、私にとってもとても勉強になりました。その上、安永老師のお話は非常に若者向きで、私も新入社員さん達も話に釘付けでした。本当に有意義な一日となり、たいへん満足致しました。
さて、私も温泉寺へ入山してまだ五年目。「下呂」というコミュニティーに於いては、まだまだ新入社員ですので自分なりに気をつけていることがあります。私共「臨済宗」をお開きになった中国の高僧・臨済禅師のお言葉「賓主歴然」という言葉です。似た様な言葉で「無賓主」という言葉がありますが、これも臨済禅師のお言葉で、意味も同じです。前者は「客と主人がはっきり区別されている。」後者は「客も主人も区別無い。」という具合に解釈されますが、全く逆の意味する言葉が、実はその本質は一緒なのです。要は、客である時は徹底して客になりきれば良いし、主人の時は徹底して主人になりきれば良いのですが、そこには何の利害関係も無く、好き嫌いも無く、綺麗汚いの思いも無く、あらゆる枠組み(色メガネ)を外した本来誰もが持ち合わせている純粋な人間性で以って接しなければならないというのです。ということは、全く平等な人間同士の心で応対することが、「賓主歴然」であり同時に「無賓主」なんですね。それが特に接客業の方には重要になってくると思いますし、寺の坊主の私にも重要なポイントなのです。寺の坊主と檀家、寺の坊主と在家、まして聖と俗などという考え方で接するだけでは、お互いの真心は伝わりませんし、第一この社会の面白さが半減しますもんね。見かけや肩書きは関係無し、皆同じ命を宿した人間ですから。
実は私は以前このことで恥ずかしい思いをしたことがあります。普段、寺に出入りされる方は大部分承知しているつもりなので、そういう方には丁寧に応対します。(当たり前ですけど。)しかし見かけない方は大体旅行か観光でいらした方なので、どうしても応対が横着になるんです。特に急ぎの用事をしている時などは、寺の歴史や由緒を聞かれても、「どうせ二度と会わない人だから。」という邪心が働くのでしょうか、とてもいい加減にあしらってしまいます。心の中では「これじゃ駄目だ」とはわかっているつもりですが・・・。ところがある日、例によって急いで掃除を終わらせて次の用事に移ろうとしている時、「あなたが住職さんですか。」「年はいくつ?」と声をかけてこられた方がありました。一見観光客のような感じだったので「今急いでますから。」と、まともに挨拶もせずに、私はその場から逃げるように立ち去りました。そして衣に着替えて法事に出かけようとした時、外では先ほどのお客さんと、うちのお婆ちゃんが仲良く喋っているではありませんか。「しまった!大事なお客さんだったのか!!」と、今さらながら挨拶をしに行きました。その方は、毎月名古屋から見える熱烈な温泉寺の信者さんだったのです。そして先ほどの自分のご無礼を私が謝る前に「いやぁ、本当にいい方がご住職になって下さって有難いわぁ。」と言われた時は、赤面の思いでした。私はすっかりその方を、ただの観光客と思い、それだけならまだしも、どこか見下した気持ちがあったのです。完全に色メガネをかけてしまっていました。
考えてみると、自分(寺の坊主)と檀家、これで一つの差別。そして檀家と観光客、これでもう一つの差別を私は自ら作り上げていたのです。私は要所要所で色メガネを使い分けていたのです。でもこれは完全に不要な物。私の見方は間違っていました。自分と他人、自分にとって都合の良い客と、どうでもいい客とどこかで判断しているうちは、真心のこもったお付き合いはできるはずがありません。この偏見的な勝手な判断は、つまらない自分のエゴによって生まれます。エゴを離れて自分の心が誰にでも同化していき、誰であっても自分の心に受け入れることができる、このような差別のないわだかまりのない心をお釈迦様は「仏心」と説かれました。しかも誰にでも「仏心」は備わっているのです。この「仏心」でもって人と接しなさいよ、という教えが先ほどの「賓主歴然」であり、「無賓主」であると思います。そういう意味で私自身、この言葉をいつでも肝に銘じているわけです。
かつてイギリスのエリザベス女王が東南アジア各国の国王をご自分の宮殿に招待された時、晩餐会で食事をしたのですが、食後、国王の一人が誤ってフィンガーボールの水を飲んでしまいました。慌てて傍にいた側近が止めようとしましたが、エリザベス女王は自分も一緒にそのフィンガーボールの水を飲まれたそうです。女王は側近達に「わが国の恥である!」と叱られますが、静かに「私のお客様は、私そのものである。お客様一人に恥をかかすことはできない。」と返答されました。普通なら腹の中で皆がその国王を笑いものにするところですが、女王は決して笑いものにしなかったのです。ということは、単なる客と主人の関係ではなく、一人の純粋な人間同士という関係で女王は接しておられたのだと思います。まさしく「賓主歴然」であり「無賓主」の世界です。
茶の湯の言葉に
「客の粗相は 亭主の粗相
亭主の粗相は 客の粗相」
という言葉がありますが、エリザベス女王の如きです。私自身が最も見習うべきことと、反省しています。
2006.06.12
青いぶどう
しばらくご無沙汰してました。いつもくだらない茶話におつきあいいただき、ありがとうございます。
先日、名前も住所も存じ上げない親子が温泉寺へお参りにみえました。50歳ぐらいのお母さんと、おそらく大学生ぐらいの娘さんです。「どこかでお会いしたことがあるんじゃないかなぁ」と思っていたら、やはりそうでした。元気よく「和尚さん、お久しぶりです!」とお二人そろって声をかけて下さいました。でも私はこのお二人がどなたなのか、さっぱり思い出せませんでした。
それもそのはず。このお二人は半年ぐらい前に急に温泉寺へ来られ、ものすごく落ち込んだ様子で、恥ずかしそうに、「このお寺で、水子供養はしていただけるのですか?」と尋ねてこられた方だったのです。こういう話はけっこうあるので、私は名前や住所は尋ねずに、境内の水子地蔵さんを指差して、「あのお地蔵さんは、水子地蔵さんですから、日にちを教えてもらえば供養できますよ。」と簡単に返答しました。いろいろ事情があるのだろうから、何も聞かずにおこうと思ったのです。
ところが、お二人はずいぶん悩んでおられた様子で「日にちはまだわかりませんが・・・。」とおっしゃった後で、くわしく事情を説明されたのです。こんなことまで聞いてもいいのだろうかと思いましたが、私はおっしゃるとおり一部始終を聞きました。娘さんは結婚はしておられないのですが、たいへん嫌なつらい思いをした結果、子供を身篭ったそうなのです。「こんなことになるなんて!」と、お二人とも涙ながらに話されました。残酷な過去の経験と、この先の不安を打ち明けられたのです。私は「これはひどい話だな」と聞いているのが精一杯でした。結局、身ごもった子供を産もうか、中絶しようかを悩んでおられるようでした。お二人は、娘さん自身まだ若いし、これからショックを乗り越えて新たな人生を望んでおられるような気がしました。だから中絶した後、子供を供養してくれる寺を探しに来られたのでしょう。ただ、そこで簡単に一人の新しい命をつぶすことをしてもいいのか、葛藤があったようです。
私はどちらとも返答しませんでしたが、(いや、返答できなかったのです。)子供を授かることができなくて悩んでいる知人や友人のことを思い出しながら、
一枚のメモをお渡ししました。ちょうどその頃読んでいた高見順さんの小説にあった詩です。
ぶどうに種があるように
私の胸に悲しみがある。
青いぶどうが
うまいワインになるように
私の胸の悲しみよ
喜びに なれ!
私はこの詩をメモに書いてお渡しするだけで、精一杯でした。お二人はこれを読んで、本当にその通りだと頷かれました。そして私の半端な知識の中にある、高見順さんの生涯を簡単にお伝えして、お二人を見送ったのです。折しも私の家内がちょうど腹に四ヶ月目の赤ん坊を身ごもっていて、楽しみにしていましたから、お二人の帰る姿を見て複雑な心境でした。
それから約半年後、つい先日私の前に姿を見せて下さったお二人は、当時とはまるで様子が違い、晴れ晴れとしていて明るく、懐かしそうに笑顔で声をかけてくださいました。「まるで感じが違うなぁ」と、驚きながら、ふと車の中に目をやると、チャイルドシートにちょこんと赤ちゃんが座っていたのです。「あっ、赤ちゃんだ!」と驚いた瞬間、「私、産んだんです。」とニコニコしながら娘さんが、その後のことを話してくれました。自分の背負った悲しみを喜びに変えられるのは、自分しかいない。そして自分の人生を、将来後悔したくないから、赤ん坊を産んで育てようと決心したのだそうです。そして「この子が丈夫に育ちますように」と、お参りにみえたのです。本当に感激しました。哀れな姿になって水子供養の対象になるのかもしれなかった赤ん坊が、今ここで元気に笑ってるんです。私まで幸せな気分になりました。ついつい「有難うございました」と手を合わせてしまいました。
お婆ちゃんとお母さんになったお二人と、赤ちゃんの幸せを、心から願いました。名前も住所も相変わらず存じませんが、「また顔を見せて下さい。」と見送りました。
高見順さんの詩を、私は益々好きになり、境内の掲示板に書いて貼っておきました。
2006.03.06
奇跡の存在
こよみでは立春を過ぎて何日かたちますが、まだまだ寒い日が続いています。
先日、小学校4年の息子の友達が何人か温泉寺に来てワイワイ遊んでいました。偶然彼らの遊んでいる部屋を通ったとき、おもしろい会話を耳にしました。「ケンカでもしているのかな?」と思うほどの口調で
「俺は3億人の中で生き残った1人だぞ!!」
と叫んでいました。最初は何のことかわかりませんでしたが、そばに保健体育の教科書が転がっていたので、「なるほど。保健の授業で人間が産まれてくるしくみをならったんだな。」と納得しました。
「俺は3億人の中で生き残った1人だぞ!!」
何だか微笑ましく、心地よい気持ちになりました。彼らがその意味をどういう具合に受け止めているのかは、わかりませんが、とりあえず「赤ん坊になれなかった2億9999人のためにも、これから先どんなことがあっても生きていくんだぞ!」とついつい余計なおせっかいを言ってしまいました。(笑)
その彼らとちょうど同じようなことを産まれた直後に言った方があります。お釈迦様です。
「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」
とおっしゃったのです。「この世の中に「私」という存在は「私」しかいない、この命は誠に尊いものだ」という意味でしょう。漢字をそのまままっすぐに直訳すると、この世の中でただ私一人のみが尊いのだ、という意味になりますが、これは間違いです。誰にでも、また人間以外のどんな生命体にも共通する「命の尊厳」を説かれたのです。
3億個の精子が、一つの受精卵になるために競争して、生き残ることができるのは、たった1つ。全滅の場合もあります。今、自分がこうして生きていることを、奇跡のように感じます。決して無駄遣いできない命の尊さを、子供達の会話が改めて教えてくれました。
最後に、京都・南禅寺の元管長・柴山全慶老師が素晴しい詩を残しておられますので、紹介します。
「一輪の花」
花は 黙って咲き
黙って 散っていく
そうして再び枝に帰らない
けれども
その一時一処に
この世のすべてを
託している
一輪の花の声であり
一輪の花の真(まこと)である
その日の心 忘れずに
婿や姑に きらわれもせず
永遠にほろびぬ
生命のよろこびが
悔いなく そこに
輝いている
2006.02.10