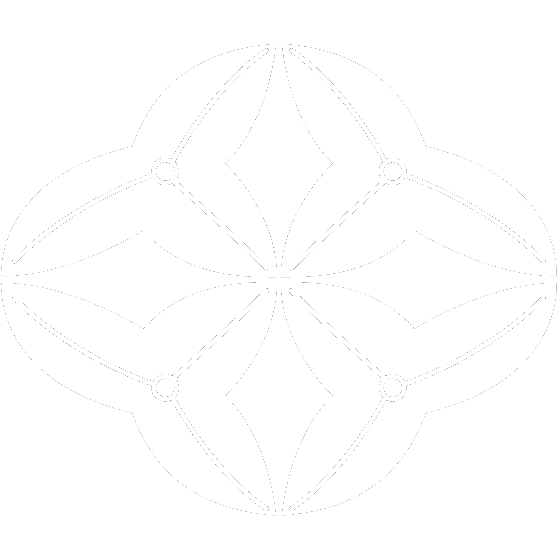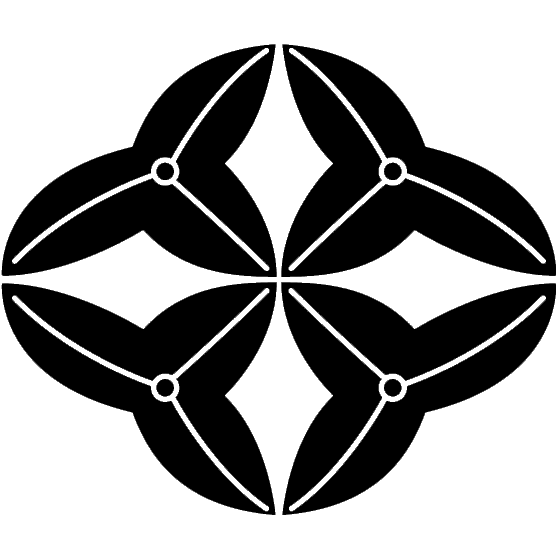
温泉寺茶話
除夜の鐘
百八の鐘、今年も是非、金(鐘)の根(音)が懐に入る初春の鐘をつきましょう!
新年百八の鐘を、金にかけて初春の最も縁起の佳いものと昔から言われてきました。
百八声、百八つと言えば、私達はすぐに除夜の鐘を思い起こします。では除夜の鐘がなぜ百八つなのでしょうか。我々人間には、生活をしていく上で、いろいろな悩みや煩いがあります。それを一つ一つ分析していくと、百八つになるというのです。それは汚れたきたない根性などであります。その汚れた根性が一年を通して、より多く積み重ねられてゆくわけです。その百八つにもおよぶ煩悩、罪過をすべて懺悔して(くいあらためて)新たな心で、より善い一年を迎えようとするのが大晦日の夜です。それを除夜と言います。
百八つの煩悩の数の根拠は、一般には
一、いかり
二、むさぼり
三、おろかさ(愚痴)
四、あなどり
五、うたがい
六、邪見
以上六つの心に、眼、耳、鼻、舌、身、意の六つの感覚がつきまとい、それが過去・現在・未来にわたるからだとされています。六つの感覚がそれぞれに互換して三十六となり、それが三世(過去・現在・未来)にわたり、百八になるわけです。(以上、温泉寺瓦版第58号より)
一年はあっという間です。もう大晦日です。あと3時間後には除夜の鐘です。みんな除夜の鐘は百八つだといいますが、私なんか百八どころかそれ以上の煩悩と、それに起因する罪過を犯していると思います。やれやれ、この一年間、いろいろなことがありました。たくさんの方にご迷惑をおかけしたことと思います。おかげ様で平成17年も無事に見送ることができそうです。有難うございました。来年もよろしくお願いします。では皆様、佳いお年を!
2005.12.31
お釈迦様、ごめんなさい。
本日12月8日は、我が大恩教主釈迦牟尼世尊(釈尊)がお悟りを開かれた、言わば成道の日です。簡単に言うと、この世に生きながらにして仏(如来)になられた日です。
インドでは本日、釈尊成道の地・ブッダガヤーにて盛大に法要が営まれます。
わが国でも、各宗各派の寺院で、本堂や床の間に出山釈迦像を祀り、それぞれに成道会という法要が営まれます。特に我々坊主にとってはとても大切な日であり、同時に忘れることのできない日でもあります。
当時釈尊は、6年間一日も怠ることなく難行苦行を徹底されました。玄奘三蔵の「大唐西域記」によると、正覚山中腹の崖の中に大きな石室があり、そこで釈尊は修行なさったそうです。しかし、長年の難行苦行の末、ここでは悟りに至ることができないと、釈尊は下山し、ネーランジャラー川のほとりでスジャータという少女に乳粥の布施を受けます。そこですっかり身も心も癒された釈尊は、そのまま静かにピッパラ樹(菩提樹)の下で瞑想に入ります。そして12月8日鶏鳴の頃、明けの明星を見て「万物と我と同根」と、お悟りを開かれたのでした。
それまでは、釈尊も自分自身の煩悩や次々に浮かびあがる欲望や怠け心との、凄まじい戦いでした。ついにそれを超越し、生きながらに仏(仏陀)となられたのです。
それにちなみ、全国の修行僧は専門道場で12月1日から8日まで、命取りの修行と呼ばれる「臘八大摂心」を毎年繰り返すわけです。私もそれで何度となく痛い目に遭いました。なにしろ自分で自分自身を追い込むのですから、苦しいのは当たり前です。その上、少しでも気を抜いているのがばれると、先輩達の鉄拳が飛んできます。一生懸命頑張って、8日の鶏鳴をすがすがしく迎えることのできる修行僧と、ただ疲労感だけが残り、8日の鶏鳴を虚しく迎える修行僧と、両方ありましたが、私はいつも後者でした。3日目頃までは気合を入れて、ガムシャラにやれるのですが、4日目頃から緊張感が途切れてきて、とにかく悟りなんてどうでもいいから、早く終わってくれ~、と思っていました。完全に惰性で迎えた6日目頃の朝、決まって「古人刻苦光明必盛大也」という言葉でもって叱咤激励されます。これはかつて白隠禅師が修行をあきらめそうになった時、禅関策進という書物をたまたま開くのですが、そのページに中国の高僧・慈明和尚(石霜楚円禅師)が座禅中に襲ってくる睡魔を打破するため、錐で自分の太ももを刺し、修行を大成させたという逸話が載っていました。そこに先の句が添えられていたのです。これを読んだ白隠禅師は、修行をバカバカしく思ってはいけない、やはり真剣に取り組まねばならないと、奮起されました。苦しみを刻めば刻むほど、その先に見えてくる光明は必ず盛大であると。
私もこの言葉を受けてなんとか8日目の鶏鳴を迎えるのですが、何年やってもなかなか昔の祖師方・まして釈尊のようにはいきません。その状態で専門道場を下山して、おめおめと温泉寺の住職をしているのですから、情けないものです。いつも今日・12月8日は反省と、釈尊に対する懺愧の念にかられます。
しっかり「自分は釈尊の弟子である」ことを自覚して、精進してまいりたいと思います。そうは言っても最近は夜になると忘年会続き。喜んで出席するたびに、クソ坊主とか生臭坊主に変身してしまうのです。哲学者・梅原猛さんに叱られる所以です。お釈迦様、ごめんなさい。
2005.12.08
月
先月の紅葉ライトアップは、おかげ様で大盛況のうちに終了できました。たくさんの方々に助けてもらい、本当に感謝しています。
その後は、残務整理と落ち葉の片付け等で、非常に忙しく、更新がなかなかできませんでした。また、12月に入ってから急に雪が降り出し、今朝は50センチの積雪で、午前中は雪かきに追われてしまいました。12月上旬でこの積雪量に驚きました。
さて、不精な私がなかなかこのページを更新しないのは、第一の理由として「忙しいから」ということにしておりますが、この「忙しい」という字は、心を亡くすと書きます。心を亡くすということは、まさしく「気が無い」ということになります。本当にやる気があれば寝ないでも更新できるはずなのに・・・(飲む時間はあっても仕事をする時間は無いんですよね~)と、自分が恥ずかしくなります。
かつて良寛和尚の伴侶「貞心尼」、京の都の「蓮月尼」と共に女流三大歌人と称された「加賀の千代」が面白い歌を残しています。
「とやかくと たくみし桶の 底ぬけて
水たまらねば 月もやどらじ」
慌しく忙しい毎日の中には、澄んだ夜空に浮かぶ月(自分の純粋な姿・または今やるべきこと)は見えてきませんよ~!ということでしょうか。
これから年末で益々忙しい日々が続きますが、心の中だけはゆったりと、自分の本分を見失わないように心がけたいと思います。
で、ホームページの更新もできるだけ努力しようと思います。(笑)
2005.12.06