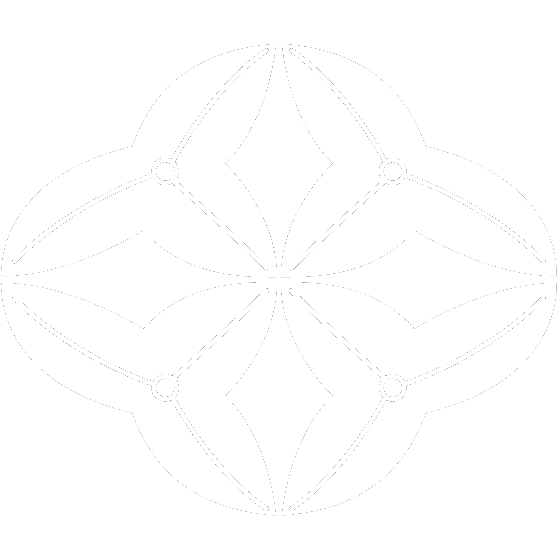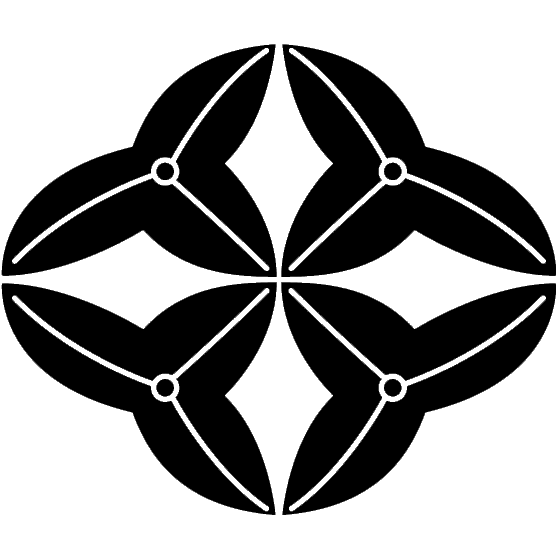
温泉寺茶話
大本山妙心寺管長猊下講演会
平成25年10月14日、午前10時30分から正午まで、あっという間に時間の経った講演会でした。
講師は大本山妙心寺(京都市右京区花園)管長であられます河野太通老大師。
お隣のお寺、泰心寺様の新住職晋山式にご臨席下さり、日程調整のため、温泉寺での講演会が叶いました!
こんな山奥のお寺で、気軽に講演をしていただけるということで、住職はじめ檀信徒の皆さん一同感激しました。
本当に雑ですが、講演内容を簡単にご紹介致します。
一、世の中のいろいろな矛盾を解決するのに一番の得策は、我慢すること。
一、我慢とは、悟りへの6つの徳目「六波羅蜜」の入り口である「忍辱」。
忍辱(にんにく)~みんなで辛抱しましょう。
布施(ふせ)~みんなで力を合わせましょう。
持戒(じかい)~みんなで決まりを守りましょう。
精進(しょうじん)~みんなで励みましょう。
禅定(ぜんじょう)~みんなで静かな心を保ちましょう。
智慧(ちえ)~みんなの心、自分の心を信じましょう。
一、六波羅蜜により気づく悟りとは、自分の心の中に「仏」を見出すこと。
一、この場所へ来ている方は皆、今、我慢をしておられる。
眠くても、私に悪いと思って、我慢して私の話を聞いて下さっている。
一、同時に皆、笑っている。つまり満足している。
一、これは皆様方の心の中の「仏」が笑っているのだ!
一、自分の心の中の「仏」に出会い、その「仏」でもって生き抜いた禅僧、良寛和尚の漢詩「毬子」を紹介します。
袖裡毬子値千金 自誇好手無等匹
有人若問箇中意 一二三四五六七
(意訳)
よく子供と手毬をついて遊ぶのだが、私にとってこの手毬は千金に値する。
自分で言うのもおかしいが、私は自分で他の誰よりも、手毬が上手だと思っている。
もし、誰かが私に、どうすればそんなに上手に手毬ができるのか質問したら、
迷わずこう答えるだろう。
一、二、三、四、五、六、七(ひい、ふう、み、よ、いつ、む、なな)と。
ただこれだけのことだよ。
一、さぁ、皆さん「仏」に目覚められたのだから、明るく楽しく生きてまいりましょう!!
以上簡単ですが、非常にわかりやすく、楽しい雰囲気でお話下さいました。改めて管長様には感謝申し上げます。貴重な機会に巡り合えて、幸せでした。
尚、この講演会につきましては檀信徒会「花園会」の皆さまにご高配いただきました。また宿泊接待を水明館様にお世話になりました。衷心より御礼申し上げます。
2014.01.19
今春開校!岐阜県立下呂特別支援学校
今年の春はお彼岸になっても寒さが残り、4月に入っていきなり初夏の日差しが続き、最近はまた小寒い日が続いています。
それでも植物達は上手に気温の変動に対応して、庭が賑やかになってまいりました。本堂裏手に広がる通称「楓月庭」はモミジの新緑が鮮やかに輝き、水屋の水路にはワサビの花の他、ヒメシャガやシャガが咲き始めています。そして毎年5月から6月にかけて目を楽しませてくれる石楠花(シャクナゲ)も咲き始めました。ところが、昨年の夏の灌水不足、追肥不足がたたり、今年はあまりつぼみを持っていません。来年は約80本の石楠花が元気よく咲いてくれるように、この夏は燃えようと思います。
ところで、去る4月9日に、岐阜県立下呂特別支援学校が開校しました。昨年度までは、飛騨特別支援学校下呂分校でしたが、新たに小学部・中学部が設立され、高等部と共に下呂特別支援学校となったのです。
これまでは私個人的にも温泉寺としましても、特に関わりがあった訳ではありませんが、昨年でしたか、あるイベントにて生徒たちが、自分たちで作った物を販売している姿を見かけました。中には顔見知りの生徒もいたので立ち寄ったところ、販売されている物の精度の高さに驚きました。湯呑や小皿などの陶芸品、エコバッグやハンカチ・小物類など、一つ一つが丁寧に仕上げられていて、幾つか私も求めました。
その後、寺に持ち帰り、役員さん等に紹介させていただきました。とても好評で、とても生徒さんが作ったものとは思えないと、皆が驚きました。ある役員さんが、湯呑などの陶器を見て、それにモミジの葉の模様が入れば、「もみじ寺」温泉寺から支援学校を発信できるとの意見を出され、早速教頭先生に申し出たところ、その念願を叶えて下さったのです。
半年ほど経った頃でしょうか、ある方から支援学校の見学に誘われ、私も出掛けました。まず、教頭先生自らが生徒と共に作陶された湯呑・小皿・そして一輪差しを拝見し、その全てにもみじの葉が直接埋め込んでありました。また、それらの陶器が出来上がるまでの様子を拝見し、生徒さんが本当にひたむきに作業している姿を目にしました。素晴らしい!の一言です。
その後、地元の方の指導による「湯ケ峰太鼓」の練習を見学させていただきました。これもまた素晴らしい!
教頭先生曰く
「この子たちは、多少時間がかかるかもしれないが、何でもできるんです!」
本当に何でもできる生徒さんたちです。教頭先生自ら生徒を引っ張っていく根気ある指導力と、常に温かい眼差しで生徒に寄り添う先生方の優しさに、一生懸命生徒の皆さんが応えている姿を目の当たりにしました。
今年に入ってから、2月のまだ寒い日でしたが、その生徒さん達が温泉寺へ課外授業に来てくれました。本堂で温泉寺の紹介をさせていただき、その後本尊薬師如来へご挨拶のお勤め、そして坐禅・写経まで体験していただきました。普段の坐禅会では私が警策(坐禅中に喝を入れる棒)を持つことはありませんが、この日はやはり教頭先生の計らいで、ほぼ全員が(勿論先生方も・・・)警策を受けて下さいました。何でも挑戦させようとされる熱意が伝わってきました。写経も、それぞれに自分が気に入った言葉を選んで、元気よく書いてくれました。
4月の開校前でしたから、この子たちが高等部の上級生として、きっと素晴らしい下呂特別支援学校を作り上げるだろうと、確信しました。
温泉寺は臨済宗という教えを受け継いでいる寺ですが、その根源的な存在である中国の臨済禅師という和尚さんの言葉に「蔭涼」(インリョウ)という言葉があります。
「穿鑿(せんさく)して一株の大樹と成さば、天下の人のために蔭涼となり去ること在らん。」
一生懸命学び、経験を積み、一本の大樹となった時、きっとその人は人のために自ら木陰となり、自身が知らず知らずのうちに、暑さの中の涼しさを与える存在になるであろう。
と個人的に解釈しています。
開校式で、「誓いの言葉」また「湯ケ峰太鼓」の披露など、はつらつとした姿を見せてくれた生徒の皆さんは、きっと将来「蔭涼」となって、私たちに「暑さの中の涼しさ」というかけがえのないものを与えて下さるだろうと信じています。
2013.04.26
飛騨屋久兵衛物語
新年が明け、お正月行事が一息つくと2月には法人会計監査並びに決算報告、確定申告・・・。そんなことをしているうちに3月に入り、先日8日は地元・湯之島区恒例大祭「薬師祭」が今年もおかげさまで大盛況のうちに無事終わり、本日、東日本大震災から丸二年目を迎えました。改めまして被災物故者の方々のご冥福をお祈り致します。
被災地のライフラインは概ね復旧したとのことですが、「復興」という文字はまだまだ見えない状況だそうです。何より、人が快適に過ごせる環境でなければ、産業も元通りにはならず、復興の兆しが見えてこないと思うのです。そう考えますと、毎年行う恒例行事が当たり前のようにできるということが、いかにありがたいことか、改めて思い知らされるところです。
この世を生き抜くことの難しさを知らされ、そのために自分が何をすべきかを考え、自分にできることを静かに成し遂げた先人が下呂にみえます。それが4代目飛騨屋久兵衛益郷(下呂武川家7代目・武川久兵衛益郷~ますさと~)です。
もともと甲斐武田氏の家臣であった武川家は、下呂に移り住んで3代目の久右衛門倍良が、武田氏菩提寺の恵林寺ゆかりの剛山祖金禅師を開山に迎え、それまで湯嶋薬師堂と称したお薬師様の御堂を寛文11年(1671年)に、正式に臨済宗妙心寺派に属する温泉寺として開きました。
当時、下呂郷六ケ村の名主を務めていた武川家ですが、元禄5年(1692年)に飛騨国が幕府直轄領(天領)になると、幕府は山林保護のために木材の伐採を禁止しました。それまで林業で生計をたてていた人たちの生活は困窮し、名主であった武川家も年貢を代納したために経済的に逼迫しました。
4代目倍行は、元禄9年に江戸へ出て、新たな事業を模索しました。それが、藩に運上金を納めて山林を伐採し、製材、輸送、販売に至る伐採請負で、その事業の場として選んだのが遥か彼方の蝦夷地(北海道)でした。これは、江戸時代前期の遊行僧として知られる円空上人が元禄4年に温泉寺を訪れており、倍行は蝦夷地の情報をある程度、円空上人から得ていたのではないか・・・とする説もあります。
こうして倍行は元禄13年(1700年)に伐採請負業「飛騨屋」を創業し、自らを飛騨屋久兵衛と名乗り、南部藩(青森県)の許可を得て下北半島の大畑にて業務を開始しました。2年後の元禄15年(1702年)には北海道・松前へ進出し、ついに広大な蝦夷地での事業を始めました。しかし飛騨屋が請け負った山林は特に条件の厳しい僻地であり、それでも経営に工夫を凝らし、後には藩からの絶大な信頼を得ることとなり、飛騨屋2代目倍正・3代目倍安へと引き継がれ、いつしか松前藩から独占的に伐採請負の許可を得るほどの豪商になっていきました。更に下呂の本店を軸に、大畑や松前の他にも秋田・江戸・京都・大阪(堺)にも支店を持ち、北前船にて木材だけでなく、豊富な海産物などの流通も手掛ける大財閥へと発展しました。
しかし、3代目倍安の頃に支配人の多額の横領が発覚、更に松前藩がその元支配人と共に飛騨屋の伐採請負の乗っ取りを画策し始め、運上金の増額を迫りました。ついにその圧力に耐えかね、倍安は伐採請負から撤退し、安永2年(1773年)に松前藩に貸し付けていた8000両を放棄する代わりに、アイヌと交易できる場所請負の権利を得ました。
しかし南下政策をとるロシアとの遭遇や、文化の違うアイヌとの交易に、場所請負の事業は困難なものでした。更に再び元支配人が飛騨屋に対して乗っ取りを画策し、倍安は幕府に対し、元支配人と松前藩を公訴。当然勝訴しますが、松前藩との関係は悪化し、4代目益郷に飛騨屋を譲ります。
しかしながら度重なる船の難破や、幕府のロシア政策、クナシリ・メナシの騒動などでアイヌを含む多くの犠牲者を出してしまい、寛政3年(1791年)、ついに益郷は蝦夷地を撤退、4代91年間に及ぶ豪商・飛騨屋のドラマは幕を閉じます。
その後、益郷は下呂へ帰郷し、名主を務めながら官材伐採の請願が幕府に認められ、寛政11年(1799年)には官材輸送を請け負いました。地道な事業努力により益郷は蝦夷地を撤退してから33年後、文政7年(1824年)についに飛騨屋の負債8200両とその利子など4003両の、合計12203両にものぼる負債を完済しました。
更に益郷は蝦夷地やアイヌ、ロシアに関する多くの記録を残しています。特に著書の「北信記聞」には、アイヌの生活・文化や、ロシアの使節「ラクスマン」の来航、漂流民「大黒屋光太夫」の返還などが記され、当時の北方事情を詳細に伝える貴重な文献となっています。
栄華と衰退の両方を知る益郷は、その陰に失われた多くの人命に対し、供養も怠りませんでした。父親である3代目倍安と共に、臨済宗中興の祖と仰がれる白隠禅師や、弟子の東嶺禅師に深く帰依し、松前・大畑をはじめ静岡県三島市「龍沢寺」や、京都・紫野「大徳寺」などに供養の跡が残されています。
下呂・温泉寺境内にも3代目倍安による略法華経15万部・般若心経1万部の供養塔(明和2年・1765年)や、4代目益郷建立の地蔵堂(文政4年・1821年)が残っています。
ただ、ただ、祈ること。昔も今も、人の心は変わってはいないと思います。
2013.03.11