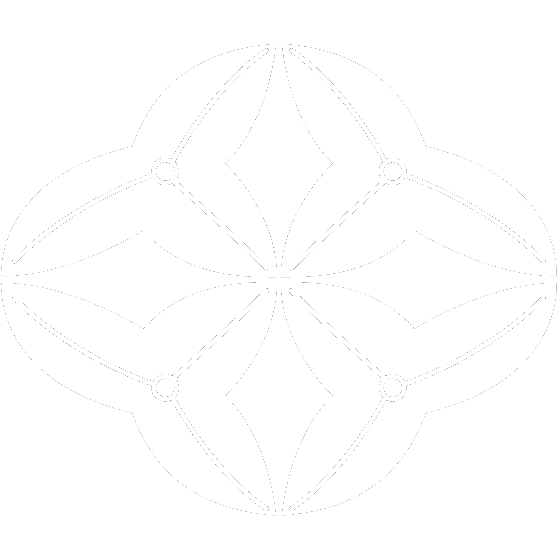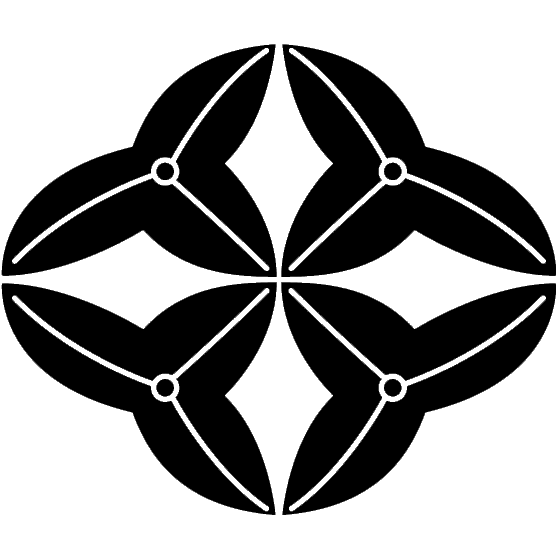
温泉寺茶話
雲を耕し、月に種まく
去る6月24日(日)は、恒例「檀信徒の集い」という言わば温泉寺の檀家総会でした。「檀家」と言わずに「檀信徒」と表現しているのは、このお寺が一般的に「檀家」と位置づけられている方ばかりでなく、その枠を超えた多くの地域の皆さまに支えられて成り立っているからです。ですからご自分の家の菩提寺の他、温泉寺に対してもご協力下さっている方が多くおみえになり、温泉寺の檀家さんは勿論のこと、そういった言わば信者さんに対しても1年に1度、感謝の意味も込めて、各種決算報告と共に一献やりましょう!という集いが「檀信徒の集い」です。
今年は4月にデビューした舞妓さんと、そのお姉さんにあたる芸妓さんをお招きし、本堂で初々しい舞いを披露していただきました。「お寺」と「舞妓さん」の組み合わせも温泉地独特の風情で、どなたも文句をおっしゃいません。それどころか、当日いらした方の中には、
「昔は何かあるとみんなが寺に寄って、境内で花見をしたり、お祭りしたり、その度に芸妓衆が踊って舞って、楽しかったよ。」
と言って下さる方もありました。温泉寺を通称「芸者寺」と呼んだ時期もあったとか・・・。とにかくそれを証明する写真(昭和5年前後)も何枚か残っていて、日本人の心の故郷ともいえるような素朴な光景を、後世にも残していきたいという役員さん達の粋な計らいで、今回の「檀信徒の集い」が実現しました。
ところで話は一変しますが、この春、真田幸村公ゆかりの地、信州上田市真田町にある「耕雲寺」というお寺さんへお邪魔させていただきました。正式には「種月山耕雲寺」とおっしゃるそうで、ご住職からその山号寺名の由来となった「耕雲種月」という禪語について、教えていただきました。
「耕雲種月」を、「雲を耕し、月に種まく」と読むと解り易いと思います。雲を耕すということ、月に種をまくということ、一体何を示す言葉でしょう?
解釈は勿論いろいろあると思いますが、雲を耕すことも月に種をまくことも、実際には不可能であり、たとえ実現したとしても何の実りも無い、つまり無駄なことであります。おかげさまで私たちの住む世界には、太陽があり、土があり、文字通り天地の恵みにより生かされています。だから雲を耕すことも月に種まくことも、余分なことで、全く必要ありません。
ところが私たち日本人は、一見無駄にみえるようなことを、とても大切にしてきました。その代表的なことが「信仰」だと思います。天を敬い、人を愛すことです。これが心の根底にあるからこそ、人が集い、お祭りもできて、とても温かい気持ちになれるのです。更にこの心の豊かさを、後世に伝えていくことができるのだと思います。
このデジタルな世の中に神社仏閣が未だ存在できていることも、「耕雲種月」の心がまだ私たち日本人の心の中に存在しているからだと思います。逆に言えば、ネット通信がチャットやフェイスブックなどで更に便利になった現在だからこそ、「耕雲種月」の心を大切に忘れないでいたいと思うのです。
これと同義にあたる言葉で「雪を担って共に井を埋む」という禪語もあります。「井戸を埋めるために、せっせと雪を運び入れる」というんですね。いくら雪を運び入れても、井戸を埋めるという目的は達成されないでしょう。しかしながら、無駄だと思えるような努力でも、コツコツと諦めずに続けていくことが大切なのだ!という先人からの叱咤激励の言葉だと解釈しています。(特に修行の身であるはずの私には辛い言葉ですが・・・)
何にせよ上田の耕雲寺様のおかげで、また1つ、心の豊かさを与えていただきました。今回の「檀信徒の集い」では何時になく懇親会が盛り上がり、男性女性問わずゆっくりと時を過ごせた感があります。ありがとうございました。
- 舞妓さん(左・菊乃さん、右・雛乃さん)
2012.07.01
ほとけの子~はなまつり~
今年も子供の日恒例「はなまつり」が開催されました。総勢60名の子供たちがお釈迦様を乗せた白象を、若宮神社から温泉寺まで引いてきました。まだお母さんに手をひかれて歩くお子さんから中学生まで、たくさん参加してくれました。遠方に居られる方も、ご家族総出で参加して下さっていて、都会の生活の中で「田舎・下呂」を想う気持ちを嬉しく感じました。
最近、子供たちが犠牲になる事故が多発しています。いろいろな災いの矢が飛び交っているこの世の中で、どうか無事に元気に成長して欲しいという願いは、どこの親御さんも想いは同じです。ただ単にお釈迦様のご生誕をお祝いするだけではなく、その願いを、誕生仏(お釈迦様生誕のお姿)に託すのが、はなまつりです。
思えば、私たちの「命」は、両親のご縁により母親の胎内に宿された時から、この世と縁が結ばれます。(宿命)
およそ十月十日の間、母親の胎内で育ててもらって、たいへんな苦労の後、母親によりこの世へ運んでもらいます。(運命)
そして、今まさにその「命」を私たちは使わせていただいています。(使命)
私たちは今、使命の真っただ中にいるんです。それをどう使わせていただくか、子供たちに伝えたいのですが、残念ながらなかなか上手に伝えることができません。
「いくら仲の良いお友達も、自分の代わりにおしっこはしてくれない。」のと同じで、
「お父さんやお母さんであっても、自分の代わりに命を使うことはできない。」
「お父さんの命を貸して。」と言われても、
「いくら可愛い我が子であっても、貸してあげることはできないんだよ。」
「だから、命って尊いものなんだよ。」
と、せいぜいこのくらいのことしかお話できませんでした。
でも、みんなで般若心経をお唱えした後、かき氷や綿菓子を食べながら、あるお母さんがお子さんに、
「どうせ使うのなら、人に優しい命であってほしいな。」
と言って下さっていました。
お子さんも笑顔で「うん!」と、大きくうなづいてくれていました。
この会話を聞いただけで大満足でした。
お手伝いいただきました湯之島子供会の皆さま、ありがとうございました。
2012.05.07
決意新たに!
昨年末、先代住職が遷化致しましてから、何となく気持ちに張りが出ず、お正月、本葬、初午祭、薬師祭、お彼岸と、目まぐるしく続く行事も、ただその場その場を何とかしのいできただけのような感じがします。
そんな中、私自身が反省せずに居れない一方、たいへんな勇気を与えていただけたのが、東日本大震災1周忌法要でした。昨年11月の紅葉ライトアップにて期間中3回のチャリティーコンサートを開催致しましたし、予てより下呂にて周囲の皆様方よりお預かりした義援金や善意を、被災地へ直接お届けしたいと考えておりました。
大先輩の宮城県・禪興寺様にご相談申し上げましたところ、震災後に私どもが瓦礫の仕分け撤去作業を少しお手伝いさせていただきました、気仙沼市・地福寺様での1周忌への参加要請をいただきました。具体的には、3月10日のお逮夜法要・震災メモリアル「鎮魂の夕べ」にて、参拝なさるご遺族の方や、大勢の学生ボランティアの皆さまに建長汁(ケンチン汁)を炊き出しして振る舞ってもらえないか、という要請でした。
喜んでお引き受けし、総代さんや役員さんと協議の結果、これまで大震災関連行事を共に作り上げてきた若手の仲間も含め、合計10名で気仙沼へ出向することになりました。結果、ケンチン汁400食の他、子供さん向けに綿菓子も提供させていただくことができました。
10ケ月ぶりの気仙沼市でしたが、港周辺は瓦礫こそ片付いているものの津波被害による廃墟が相変わらずそのまま立ち並んでおりました。「復興」という文字が本当にほど遠く感じられました。地福寺様周辺も瓦礫は取り除かれておりましたが、何も無くなった所に、何とか修復なさった本堂がポツンと淋しそうに建っていました。何も無くなった境内に「祈りの広場」を設けられ、観音様が海の方を向いておまつりされていました。
私たちは境内の「祈りの広場」にて炊き出しをさせていただきましたが、地福寺様の役員さんや、女性部の皆様方が、ご自身もそれぞれ被災なさってたいへんなご不幸に遭われている中で、献身的にお手伝い下さり、その前向きなお姿に感銘を受けました。
綿菓子ブースでは、地元・階上中学校の生徒が10人ほど集まってくれ、「今日は卒業式でした。遠くから来てくれてありがとう。」という言葉をかけてくれました。遠目にその子たちを見ていると、ふざけあったり、じゃれあったりして、どこから見ても普通の中学生なのですが、津波で亡くした友だちや親族に対して、一生懸命手を合わせていました。彼らもそれぞれにいろんな想いを交錯させながら、これまで一生懸命過ごしてきたのだと思います。
昨年は震災直後、10日遅れでの卒業式で、梶原裕太君があまりにも立派な答辞を述べてくれました。(前回の茶話にて紹介させていただいています)その後輩にあたる子供たちでしたから、きっとしっかり前を向いて、この世の大自然と真摯に向き合って生きていってくれることと思います。
お逮夜法要「鎮魂の夕べ」のクライマックスに、地福寺ご住職の法話を拝聴しました。
「冷酷な言い方かも知れませんが、私たちはこの世に生きている限り、必ず命の終焉を迎えます。自然災害や事故だって、何処にいても遭遇する可能性があるんです。しかしながら、どんな境遇にあっても、めげない!逃げない!くじけない!とにかく前を向いて歩んで行こうじゃありませんか!」
同じく被災なさった地福寺様の熱いメッセージに、参拝なさっていた全ての方が涙しながらうなづいておられました。
3月11日、1周忌を迎えて多くの被災者の皆さまが、また改めて復興の第一歩を歩みだそうとしておられます。その姿勢にわが身を振り返るとただただ反省です。一方で折角授かったこの命を決して無駄にすることなく、いつ死が訪れても後悔しないよう誠実に生きていかねばならぬと思います。自分自身の命を寿ぐことができますように!(命の終焉=死=寿命=命を寿ぐこと)
四月は新たな門出の季節です。振り返りますと私が温泉寺に入山して丸10年が経ちました。当時小学校2年生だった近所の子も、遠方の大学へ発ちました。嬉しいような淋しいような・・・。
昨日は舞妓として門出を迎えたお二人が、温泉寺にお参りに来てくれました。それぞれに決意を新たにして頑張ろうとしている姿を見て、こちらも励まされます。
どうか皆様方の弥栄を祈念申し上げます。
2012.04.02